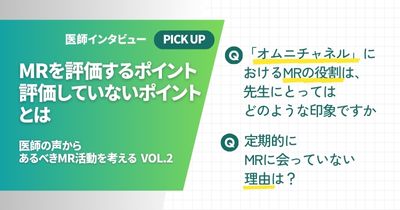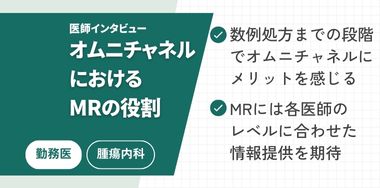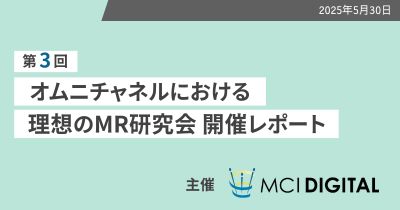医師がMRに期待することとは?医師の声からあるべきMR活動を考えるVol.1
DM白書ラボでは、さまざまな施設、診療科の医師が薬剤の情報収集時の行動や行動の背景について詳しくお話を伺いインタビュー記事として公開しています。本記事では、これまでのインタビュー内容から「医師がMRに期待すること」についての医師の声をまとめてご紹介します。
「MRの情報提供以外に対する期待事項と現状の評価」についての調査結果※1では、MRに対する期待値は「副作用や製品回収などが起きた際の対応」、「自身の専門や興味に合わせた情報提供」、「薬剤に関する相談」の順で高いことが明らかになっています。
本記事では、医師がMRに具体的にどのような期待をしているのかを、DM白書ラボで実施した医師インタビューの中から重要なポイントをピックアップしてご紹介します。ぜひMR活動の参考としてください。
目次
MRへの期待事項では「副作用や製品回収などが起きた際の対応」が最も高い期待値
「MRの情報提供に対する期待事項と現状の評価」(DM白書2023年冬号)※1では、MRに対する期待値は、「副作用や製品回収などが起きた際の対応」、「自身の専門や興味に合わせた情報提供」、「薬剤に関する相談」の順で高いことが明らかになっています。
そこでDM白書ラボのインタビューで得られた具体的な医師の声を項目ごとに紹介します。
医師の声「副作用や製品回収などが起きた際」に期待する対応
Q.MRにはどのような点を期待しますか?
MRにお願いしたいことは、「副作用や製品回収が起きた際の対応」や「自身の専門や興味に合わせた情報提供」「薬剤に関する相談」「他施設の医師とのネットワーキングのサポート」などですが、お話したように、今の病院では顔が思い浮かぶMRがほとんどいません。ただ、MRなら誰でもいいというわけではなく、優秀なMRに限った話です。
- K先生(大学病院/消化器外科/30代/新薬の処方意向:他の医師の処方経験を参考にし、処方を検討)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編
Q.MRの対応が薬剤使用に影響することはありますか?
有害事象が起きた時のMRの対応が、その後の薬剤使用継続に影響することはあります。MRの対応が積極的で、早ければ早いほど助かりますね。新薬を早い段階で使うほど、有害事象に関する情報収集が必要なケースが多くなるので、MRを質問攻めにすることもあります。対応をしっかりしてくれると信用できるので安心感があります。情報提供が少ない場合は、不親切だなと思いますね。
Q.先生がMRに期待されている点を3つ挙げるとどれになりますか?
まずは「副作用や製品回収が起きた際の対応」ですね。2つ目は、「他施設の処方状況」です。他施設の状況でも副作用情報を把握できますので。得られた事例を意識しながら診療できるので、曖昧な情報でも助かります。3つ目は、「薬剤を切り替えるポイントとタイミングについての事例提供やサポート」で、これにより薬剤を切り替えやすくなります。
- D先生(公立病院/血液内科/40代/新薬の処方意向:新薬は進んで採用処方を検討)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編
Q.では、逆に副作用が出た時のMRの対応によって製薬企業への信頼感が増すということはあると思いますか?
あると思います。MRに期待していることは副作用情報の提供なので、副作用について質問したときに、製薬企業が持っている論文化されていないデータなどについて情報提供してくれると信頼感は増します。MRは、常に情報提供に来なくてもいいですが、何かあった時に質問には答えて欲しいと思っています。
- I先生(大学病院/乳腺外科/40代/新薬の処方意向:新薬は進んで採用処方を検討)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.1 大学病院 勤務医編
医師の声「自身の専門や興味に合わせた情報提供」に期待する対応
処方の意思決定にMRは重要でしょうか?
重要だと思います。わたしが悩んでいることに対して、講演会や記事、詳しい先生などを紹介してくれるなど、こちらのニーズに合わせて情報提供してくれる点は、MRの重要な役割だと思います。また、全国Web講演会では得られない、地域の情報をMRが持っているという点も重要です。
実はつい先日施設を異動したのですが、新しい環境では困ったときに顔が思い浮かぶMRとのコネクションがありません。以前のように関係性を作っていくのは、今の環境では難しいのではないかと感じています。ですが、3rdPartyではMRの代わりになれないと思います。
先生にとって、優秀なMRとはどんな方でしょうか
患者のことを考えて一緒に解決してくれるMRです。MRからの情報には客観性があり、情報収集するチャネルのアドバイスもしてくれるので、相談しやすく信頼感もあります。ですが、実際にはしつこいなと思うMRがほとんどで、薬剤を売ろうとしすぎているように感じます。わたしにとってはあまり関心のないパンフレットを置いていったり、開口一番自分の話をしだして、まずわたしの話を聞いてくれる姿勢がない方は、今後何かを相談したいという気持ちにならず残念に思います。
MRは自社の製品を売ることだけを前面に押し出さず、医師が困っていることを患者のために一緒に解決してくれる存在であって欲しいと思います。
- K先生(大学病院/消化器外科/30代/新薬の処方意向:他の医師の処方経験を参考にし、処方を検討)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編
先生がMRの役割として期待する「人間的なつながり」とはどのようなことでしょうか?
MRには、医師とのコミュニケーションを通じて「MRだからこそ集められる情報」を収集し、還元してくれることを期待しています。具体的には、「他の施設の先生がこの薬剤を実際に使ってみたところ、こういう結果でした」といった現場レベルの情報が、色々な施設を回っているMRにしか集められない貴重な情報だと思います。
- N先生(公立病院/小児科/40代)
- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.3‐
先生がMRに期待することはどんなことですか?
医師が医療系ポータルサイト上でどのような情報収集をしているかを担当のMRが把握して、それを考慮した情報提供を行うとよい
各医師の好みなどに沿ってチャネルを選んで情報提供することは比較的精度高くできると思いますし、私としてもありがたいです。医師によって働き方、忙しい時間帯、好むチャネルなど様々ですので、直接MRから情報を届けるべきか、Web講演会が視聴できるかなど、状況は変わってくると思います。
インターネットサイトで調べている疾患情報などをヒントに、「この疾患について調べているならば、高齢の患者さんがいるのでは」と考えて「社会保障制度の最新の改定情報を届けてくれる」といった動きはありがたいです。
- H先生(公立病院/脳神経内科(神経内科)/30代)
- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.2‐
「オムニチャネル」におけるMRの役割について、先生としてどのようなことを期待しますか?
MRに期待するのは、興味はあるが自分で調べても見つからないような情報を提供してくれることです。
例えば、国内の学会における小さな発表や地方単位での講演会の開催情報など、インターネット検索ではヒットしない情報もあるので、そのような情報をMRが提供してくれるとありがたいですね。
- S先生(公立病院/腫瘍内科・乳腺外科/甲状腺外科/50代)
- 製薬企業が考える「オムニチャネル」と「オムニチャネルにおけるMRの役割」は医師にとって望ましいのか‐公立病院勤務医編Vol.1‐
医師の声「薬剤に関する相談」に期待する対応
MRに定期的に会っていない理由はありますか?
コロナ禍以前は院内にMRがいましたが、コロナ禍で訪問規制となりMRに会う機会が無くなったためです。MRから手紙が来ることもありますが中身は見ません。
特に用事がないときに会っても時間がもったいないですし、必要な情報を得られるとは思えません。
MRからは、初めて使う薬剤の注意事項などを聞きたいのですが、知っているMRがいない時はインターネットサイトまたはHOKUTOで情報収集しています。
ただ、薬剤に関する周辺情報も知りたいので、MRに聞けるといいのに、とは思います。
- K先生(大学病院/消化器外科/30代/新薬の処方意向:他の医師の処方経験を参考にし、処方を検討)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.6 大学病院 勤務医編
処方の意思決定においてMRからの情報提供は重要でしょうか?また、今MRから受けている情報提供は、MR以外からでも代替可能でしょうか?
わたしは、MRからの情報提供は重要だと考えていますし、MRは代替不可な存在と考えています。人によって好き好きかとは思いますが、わたしはMRと話すことで頭の中に情報が入りやすくなります。MRと直接会って情報提供を受けることが、わたしにとっては大切なことです。
- A先生(大学病院/脳神経外科/50代)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.3 大学病院 勤務医編
Q. MRの対応が薬剤使用に影響することはありますか?
有害事象が起きた時のMRの対応が、その後の薬剤使用継続に影響することはあります。MRの対応が積極的で、早ければ早いほど助かりますね。新薬を早い段階で使うほど、有害事象に関する情報収集が必要なケースが多くなるので、MRを質問攻めにすることもあります。対応をしっかりしてくれると信用できるので安心感があります。情報提供が少ない場合は、不親切だなと思いますね。
Q.「(3)数例の処方をしている」段階ではいかがでしょうか?
この段階は実体験が重要です。添付文書などには、実際に副作用が「どの時期に起きるか」「どのような症例で起こりやすいか」などの情報はあまり書かれていません。そのため、実際に処方して得られた情報やMRが収集した情報、インターネット講演会からの情報がより重要です。
Q.この段階では、MRからの情報が重要ということでしょうか
はい。「薬剤による典型的な副作用をコントロールするために、他施設ではどのような工夫をしているのか」「起きている副作用が典型的なものなのか、それとも非典型的なものなのか」などについて、MRに確認します。
- D先生(公立病院/血液内科/40代)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.2 公立病院 勤務医編
MRと直接面談することの意義
薬剤情報収集の観点では、MRとの直接面談がなくても特に困ることはありません。実際、コロナ禍にMRの訪問がなくなっても、特に困ることはありませんでした。
それでも、MRへ直接質問したい点が思い浮かぶことがあり、MRとのディスカッションなどを通して薬剤の理解が深まっていくことに意義があると感じています。
また、直接面談することにより処方につながった薬剤や処方が増えた薬剤もあり、何度も熱心に訪問するMRの企業の薬剤と、他の同じクラスの薬剤とでは処方に差が出ることもあります。
- A先生(市中病院/循環器内科/40代)
- 【医師の働き方改革 CASE02】働き方改革を踏まえたMRからの情報提供への期待
臨床試験の結果だけではわからない「実はこういう事例があった」「あの大御所の先生はこのように言っていた」といった紙資材やインターネットサイトには掲載されない内容を、MRから得たいという強い期待があります。
また、「他の医師が使用している薬剤情報を得たい」「他の医師との講演会のセッティングなど、人とのつながりを作ってくれる」ことなども、MRに期待されています。
- O先生(大学病院/総合診療科/40代)
- 【医師の働き方改革 CASE01】時間外労働規制に伴う薬剤情報収集への影響
医師の声「他施設の医師とのネットワーキングのサポート」に期待する対応
MRとの関係性も重要ということですが、先生にとって好ましいMRとはどんな方でしょうか?
しつこい営業をかけてこない人ですね。普段忙しいので、グイグイ来られると引いてしまいます。
実利的なところでは、研究会などを企画してくれると、普段会わない先生と会って、話が弾んで自身の研究に繋がるというケースもあるので、人脈を形成できる場を提供してもらえると非常にありがたいですね。
Q.MRに期待しているものを教えてください
最もMRや製薬企業に対して期待したいのは、製薬企業主催のイベント(セミナー、説明会など)の企画・開催です。
副作用への対応は自身でするしかありませんし、薬剤や診療に関することなどは同僚の信頼している先生に相談します。また、他施設の処方状況は、現地開催の講演会などで参加されている先生方から直接情報収集しています。
ですが、講演会は自分で開催することができませんし、ほかの医師とのネットワーキングにもつながる大切な機会という一面があります。イベントの企画・開催にすべての期待を寄せています。
- K先生(大学病院/循環器内科/30代)
- 【MR未リーチ医師インタビュー】処方検討時に必要な情報と利用チャネル Vol.4 大学病院 勤務医編
ラボ編集部からのコメント
MRへの期待事項は多数挙げられており、「定期的に会っているMRがいない」医師であっても、MRへ何らかの期待を寄せる医師は少なくありません。MRへの期待事項を把握することが、オムニチャネルにおいてMRの担う役割を定義するために必要なことだと言えるでしょう。
今後明らかにしていくこと
次回は、医師がMRを評価するポイント、評価していないポイントとは医師の声からあるべきMR活動を考えるVol.2 を紹介します。
(文:松原)