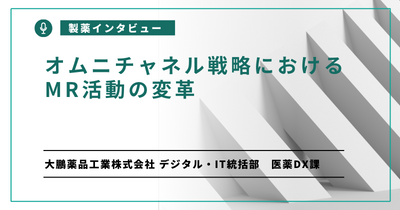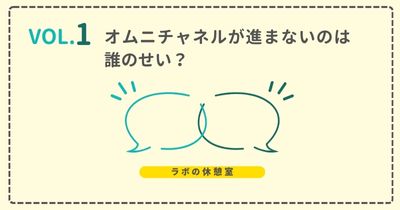MRのオムニチャネルカルチャー醸成に向けた取り組み(アステラス製薬株式会社)
今回は、アステラス製薬株式会社のお二人にインタビューを行いました。
オムニチャネルをカルチャーとしてMRに根付かせるために、具体的にどのような取り組みをされたのかお伺いしています。
なお、本記事はインタビューにご協力いただいたお二人の個人的な見解に基づくものであり、お二人の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願いいたします。
取材年月 2025年3月
目次
カスタマーエクセレンス部、オムニチャネルアクティベーショングループ所属:金保様
コマーシャルケイパビリティ CL&D, フィールドエクセレンスチーム所属:金子様
※所属・役職等は取材時点のものです。
所属チームのミッション、役割、業務内容と、お二人の役割について紹介
お二人の社内での役割について教えてください。
| 金保様 |
カスタマーエクセレンス部、オムニチャネルアクティベーショングループに所属しています。グループのミッションは、日本の医療に、最適な情報提供モデルの構築および実行を通じて貢献することです。 私は、主に消化器がんおよび血液がん領域におけるオムニチャネル戦略の立案と実行を担当しています。デジタルとリアル、本社の機能などさまざまなチャネルをシームレスにつなぎ、顧客に対してより効率的でインパクトのある情報提供を実現することで、顧客のエンゲージメントを高めていくことが主な業務です。 |
|---|---|
| 金子様 | コマーシャルケイパビリティの フィールドエクセレンスチームに所属しており、グローバル組織ではありますが、日本地域の人材開発を中心に取り組んでいます。グローバルでの決定事項をそのまま展開するのではなく、日本のコマーシャル部門のさまざまなチームとも協働して、ニーズや状況に一番合う形に調整して展開していくのが大きなミッションです。 |
MRのオムニチャネルカルチャー醸成に関する社内体制と役割分担
MRのオムニチャネルカルチャーを醸成していく上でのお二人の役割や社内体制を教えてください。
| 金子様 |
新しいツールの開発も含め、オムニチャネル活動の仕組みの立案・構築は主にオムニチャネルアクティベーショングループが担い、その実現に向けた能力開発やカルチャー醸成、組織開発に向けた取り組みを、フィールドエクセレンスチームと協働で進めているというイメージです。 国内外を含め多くの部門が関連していますが、カルチャー醸成の観点で特に大きく関わっているのはこの2つの組織です。 |
|---|---|
| 金保様 |
アステラスは今まさにオムニチャネルの浸透を図っている段階ですので、実際に顧客と対面するMRに対しては、「オムニチャネルとは何か?」という基本的な理解を深めてもらう取り組みを進めています。 ここで重要なことは、ツールの説明や方法論だけでなく、「オムニチャネルによって実現できる世界観」もしっかりと伝えていくことだと考えています。 また、MRだけでなくマーケティング部門に対しても、オムニチャネルによる戦略立案の支援を積極的に行っています。 |
今回、オムニチャネル「戦略」、オムニチャネル「マーケティング」ではなく、オムニチャネル「カルチャー」というテーマでお話をお伺いしますが、社内においてもこの言葉で推進されているのでしょうか?
| 金子様 | オムニチャネル活動のゴールの1つには、顧客エンゲージメントの向上があります。そのため、オムニチャネル活動の推進には、顧客視点を重視した組織文化の構築が不可欠です。カルチャーという言葉は使用していませんが、組織文化醸成も意識しながら、取り組みを進めることが重要と捉えています。 |
|---|
他部門で、最も関わりのある部門は営業部門でしょうか?
| 金保様 |
はい。営業部門とはコミュニケーションを密に取り、エリア単位でオムニチャネル活動を推進しています。特に、営業部長※1 とはかなりの頻度でコミュニケーションを取り、高い意識でオムニチャネルやデジタルツールの推進に取り組んでいただいています。 オムニチャネルアクティベーショングループは、オムニチャネル活動のための新しいツールの開発・活用推進にも力を入れており、この取り組みは現場のメンバーを巻き込んで推進しています。各グループ(営業所)から推進メンバーを1名選出し、組織内でのツールに関する情報提供や研修、サポートを行っています。組織内の全員がそのツールを使いこなせることを目指しています。 また、各グループマネジャー※2 も、オムニチャネル活動の推進に積極的に取り組んでおり、現場と本社部門とで一丸となって取り組んでいます。
|
|---|
マーケティング部門との連携も必要になると思いますが、どのように進められていますか?
| 金保様 | マーケティング部門を含む各ブランドチームに我々が横断的に配置されており、所属こそ違えどワンチームとなり密に連携しています。具体的には、「この情報を届けるために最適なチャネルは何か」「チャネルの連動性を計画的に戦術に落とし込んでいこう」といったオムニチャネルの重要なエッセンスについて、協力して取り組んでいます。 |
|---|
MA部門とも連携されているのでしょうか?
| 金保様 |
はい。先に述べたブランドチームにはMA部門も参画しており、連携を深めています。 オムニチャネルにおいては顧客を中心に置き、顧客体験の向上を図っています。顧客のその時々のニーズに応じてチャネルを自由に選択でき、顧客がアステラスの製品に対して必要な情報をタイムリー、かつシームレスに得られる状態を実現するためには、MA部門とも協働して取り組むことが不可欠です。 |
|---|---|
| 金子様 | 顧客にとってどれだけ良い体験になるかを突き詰めると、顧客に関連するあらゆる部門が、顧客視点で連動し、シームレスな状態をうまく作ることが必要だと考えています。 |
各部門で役割やミッションは異なると思いますが、その中で、部門間の連携がうまく進んでいる要因は何でしょうか?
| 金保様 |
個人的な感覚ですが、「薬を届けることで患者さんに貢献したい」という思いは部門に関わらず共通のものです。今この時代において、そのために必要な取り組みとしてオムニチャネルを推進する点に多くの方が共感していることが最大の要因ではないでしょうか。組織全体で見ても、この方向性は強く打ち出されています。 コマーシャルとメディカルに焦点を当てると、これまではこの2つが完全に分離された組織体系であったため、お互いに深い連携を避けて活動していました。 しかし、「顧客体験や顧客セントリシティで考えると、適切なあり方はそうではないよね」というメッセージが強く発信されました。この背景には、グローバルのコマーシャルのトップとメディカルのトップが、密に話し合いを重ねてきた経緯があると聞いています。日本においても、日本のコマーシャル部門とMA部門合同のタウンホールミーティングが開催され、その中でも同様のメッセージが強く発信され、より密接に連携しながら活動する方向性へと舵を切りました。 また、組織体制そのものも進化しました。コマーシャル部門とMA部門がともに集うブランドチームという組織を作り、1ブランドに対するチームとしてコミュニケーションを取る機会が増え、それがうまく回り始めているのだと思います。 当然ですが、この取り組みに際して、コマーシャル部門とMA部門の線引きについての整備も行っています。協力し合うためには、両者の役割分担を明確にすることも不可欠な要素だと思います。 |
|---|
MRのオムニチャネルカルチャー醸成(1) 4つのキーメッセージを発信
MRのオムニチャネルカルチャーを醸成していく上での具体的な取り組みを教えてください。
| 金子様 | 全体的な取り組みも含めてお話しします。最初に最も力を入れたのは、「組織として変化に適応しながら顧客志向を重視することに取り組んでいく」という明確なメッセージを共有し、全員が同じ「オムニチャネルで実現するビジョン」を描けるように浸透させていく、という点です。 |
|---|
共有されたメッセージはどのようなものでしたか?
| 金子様 |
顧客の価値観も含め、私たちを取り巻く環境が大きく変化してきているという前提を伝えた上で、次の4点をキーメッセージとして共有しています。
|
|---|
このようなメッセージは、どのように作り、どのように伝えられたのでしょうか?
| 金保様 | メッセージは、オムニチャネルアクティベーショングループが中心になり、部門のリーダー層が議論を重ねて作られました。そして、年度初めのタウンホールミーティングの中で、「アステラスはオムニチャネルで顧客エンゲージメントを高めていくんだ」と発信しています。 |
|---|---|
| 金子様 | その後もさまざまな場面でリーダー層からコミュニケーションを積極的に取り、複数の切り口や多様な視点からメッセージを発信しています。また、共感を得る、自分ごと化して欲しいとの観点から、メッセージの発信だけでなく、オムニチャネルに対する意見を共有する場も設けました。 |
意見を共有する場とは、MR同士のディスカッションを行ったということでしょうか?
| 金子様 |
はい。意見を共有する場として、MR同士のディスカッションを行いました。メッセージの受け手一人ひとりが考えていることや感じていることを大切にするため、短いながらも研修内で時間を確保し、オムニチャネルが実現できたときに、「顧客にどのような変化が訪れるのか」、「そのとき顧客がどのような感情を抱くのか」、「自分たちにとってそれはどのような意味を持つか」という意見を共有し合う場を設けました。 オムニチャネル自体が抽象的な概念であり、当然人によって捉え方が異なるので、さまざまな意見に触れることが重要だと考えています。 また、対話をすることで、同じ目標に向かうという仲間意識も強くなりやすい、自身の考えを言語化することで解像度が高まる、というメリットもあります。 加えて、グループマネジャーの皆さんの感度が高く、研修以外でも、営業所内でコミュニケーションを図り、また事例共有などの場を設けてくれています。このような活動を通じて、オムニチャネルのメッセージが少しずつ浸透していったのだと思います。 |
|---|
MRのオムニチャネルカルチャー醸成(2) カルチャー醸成のサポート
オムニチャネルカルチャー醸成に向けたサポートについて教えてください
| 金子様 |
オムニチャネル活動の実現は、MR活動の考え方や進め方を進化させていくことでもあるため、メッセージの発信や研修の実施だけでは実現できないと捉えています。そのため、実際にMRの皆さんが環境変化の中で一人ひとりの顧客に向き合い、取り組み&振り返りを継続して行い、実践しながら良い形を見つけていくことを重要視しています。 我々の方では、ノウハウの共有に加え、「オムニチャネルの取り組みが顧客にとって良い体験をもたらしていること」や「患者さんへの貢献にもつながっていること」、「変革を進められたことを皆で祝福できる場を持ちたい」という意図で、年度の終わり頃に好事例(小さな成功)を全体で共有する機会を設けました。 継続的な支援と機会提供をしたかったのですが、重要度の高い他のプログラムとの兼ね合いや現場活動の時間を確保する観点から、本社部門主導による学習機会を継続的には作れないという現実がありました。 しかし、各営業部やグループ内で自発的にオムニチャネル活動の好事例を共有するなど、現場の皆さんによる主体的な活動が数多く行われており、オムニチャネルカルチャーが根付く上での強力な推進力となっています。こうした取り組みが生まれている事自体が、カルチャーが根付いてきている証左とも捉えています。 |
|---|---|
| 金保様 | 今の話に加え、前述のオムニチャネル関連ツール推進メンバーとのコミュニケーションの場を月1回設定し、現場で起きている事例の共有や課題について議論することができている点も大きいと感じています。 |
現場のマネジャーも文化醸成に大きく貢献しているとのことでしたが、皆さんの方でマネジャーを対象にスキル開発等の支援を行ったのでしょうか?
| 金子様 | オムニチャネル活動の推進と並行して、グループマネジャーたちを対象に変革を引き起こし、チームやメンバーをサポートしていくためのスキルや、方法論についての研修機会を提供しています。変化に対する受け取り方は人によって異なります。皆が変革に前向きに取り組めるよう、マネジャーがそれぞれに合わせた関わり方、対話を行うことを重要視しています。 |
|---|
MRのオムニチャネルカルチャー醸成(3) MRのオムニチャネル活動のサポート
MRのオムニチャネル活動を推進するためにどんな活動をされましたか。
| 金保様 |
一人ひとりのマインドだけではオムニチャネル活動の実現は難しいため、仕組みの構築や新規システムの導入・推進も進めています。これは、先ほどお話した各営業所の推進メンバーと協働し、現場の声を反映しながら行いました。加えて、MA部門をはじめとした関連部門と協働できるような体制や仕組み作りも行っていきました。 具体的には、MRのオムニチャネル活動を支援するAIツールの活用やさまざまなデータを素早く確認できる環境整備、情報収集や自己学習ができる社内サイトの立ち上げなどです。 また、MRが行動する際のポイントを学ぶための研修や、模擬的な体験やディスカッションを通じて実践的な感覚をつかむための研修も実施しました。 |
|---|
MRのオムニチャネルカルチャー醸成への取り組みによる成果
取り組みの中で得られた成果や気づき、課題を教えてください。
| 金子様 |
現場にいる人たちがオムニチャネル活動に意識を傾け、熱意を持って取り組んでいる状態になっていることが一番の成果だと思います。 オムニチャネル自体の成果を定量化することは難しいのですが、定性的な例では、データや情報をこれまで以上にMR活動に反映させることで、面会が難しかった顧客との面会が確保できたり、顧客から「ちょうどその情報が欲しかった」というフィードバックをもらうことができたりといった、ポジティブな事例が増えてきています。 このような事例が、「オムニチャネル活動の実践が、顧客の体験をより良いものにできる」という実感につながっていると感じています。 また、本当に多くの部門やエキスパートたちが一丸となってオムニチャネル活動の推進に取り組んでいます。この取り組みを通じて部門間連携が活性化し、組織としての一体感がより高まったことも1つの成果と考えています。 こうして振り返ると、私たちが企画し展開してきたさまざまな取り組みはきっかけ作りでしかなく、実際には現場のMR、マネジャーが自分たちで考えて取り組んでいることが、オムニチャネルカルチャーの醸成や活動の推進において最も効果的な活動であったと強く感じます。 |
|---|---|
| 金保様 |
「やらされ感」というよりは「取り組んでいこう」、という前向きなマインドに最初の段階で変わっていったことが大きいと思います。 推進メンバーに関しては、始めはある程度の強制力をもって進めたことで現場の成功事例が挙がってきた部分も大きいのですが、自発的な取り組みに徐々に変わっていったことは成果だと思います。 成功事例を共有する場を設定したところ、任意参加にもかかわらず非常に多くの人が集まったので、やはり感度は高くなっていると感じています。 また、客観的なデータとしてツールをうまく活用している部分では実績も上がってきているという数字も出始めており、好事例が挙がってきている点からも成果を実感しています。 |
今後のオムニチャネル推進への展望
今後どのようにオムニチャネルを発展させていく予定かをお聞かせください。
| 金子様 |
組織一丸となってオムニチャネルに取り組むことで、アステラスのMRが業界No.1の顧客エンゲージメントを獲得している集団となることを目指しています。 個人的な意見になりますが、オムニチャネルというとデジタルチャネルに注目しがちですが、私自身はヒトによる顧客との対話の重要性を改めて感じています。デジタルチャネルと生身のMRによる対話のシナジーの最大化が1つのゴールであると確信しています。 医師を取り巻く環境も大きく変わってきている状況です。先生方一人ひとりにとってのベストな体験を提供することで患者さんだけでなく、日本の医療全体にも貢献していきたいと考えています。 |
|---|---|
| 金保様 |
アステラスが、顧客エンゲージメントを最も獲得している集団となるために、ますますオムニチャネルを発展させていきたいと考えています。そのために、MRをはじめとした社内ステークホルダーのマインドを継続的に高めていくこと、それを実現できるような環境作りにも注力していきたいと思っています。 また、今あるチャネルだけがすべてではなく、日々新たなソリューションが登場しています。「何が顧客にとって最適なのか」を常に探求し、新しいテクノロジーも積極的に取り入れていきたいと思います。 ブランドの戦略に対しても、これを達成するために最適なオムニチャネルとは何なのかを追究し、顧客体験をさらに向上させることで大きな成果につなげていきたいと考えています。 |
(文:下村)
●合わせて読みたい記事