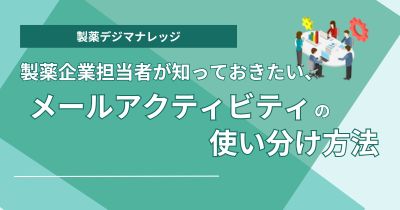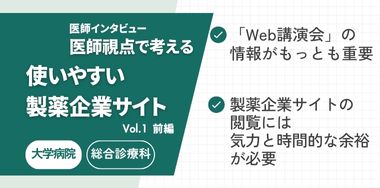製品ブランドチームによるオウンドチャネル活用促進のための3つのポイント 〜製薬企業におけるデジタルマーケティング実践の最前線〜
はじめに:なぜオウンドチャネル活用が重要なのか
日本の製薬業界においてもデジタルシフトが加速しており、医療従事者とのコミュニケーションは、従来のMR(医薬情報担当者)訪問や電話だけではなく、Web講演会やWebサイト、メール配信、CRM(顧客管理システム)を活用するデジタル施策が不可欠な時代となりました。
その中で「オウンドチャネル」、すなわち自社が保有し運営するWebサイト(オウンドサイト)、メール、CRMなどは、3rdPartyにはない大きな強みを持っています。
自社ブランドや製品のメッセージを、ターゲットである医師をはじめ医療従事者にオムニチャネルでコントロールしながら、継続的かつ戦略的に届けることができるからです。
しかし現場のブランド担当者からは、「使い方が難しい」「コストや準備期間(リードタイム)が不明確」「外部媒体の方が気軽に使える」といった声も多く、せっかくの自社リソースを活かしきれていない現状があります。
本記事では、製品ブランドチームがオウンドチャネルを積極的に活用するための3つのポイントについて、課題整理から具体的な解決策、実践ステップまでを解説します。
目次
1. 「オウンドチャネルでできること」を明確にし、施策メニュー化で使いやすさを実現
現場のよくある課題
- ● どこまでの施策がオウンドチャネルで実現できるのか分からない
- ● 施策ごとの仕様調整が煩雑
- ● 社内の確認や調整に想定外の手間がかかる
製品ブランド担当者がオウンドチャネル活用に踏み切れない最大の理由は、「オウンドチャネルで何ができるのか」が不明確なことです。例えば「Webサイトで製品キャンペーンページを作りたい」「Web講演会の集客をしたい」と考えたときに、
- ● どこまでの表現や機能が許容されるのか
- ● 医薬品プロモーションコードや社内規定の範囲でどんな施策が可能か
- ● 他社の事例や成功例はあるのか
といった点が曖昧なまま、担当者ごとに“手探り”で進めているケースが多く見られます。
解決策:「ユースケースの特定」と「施策メニュー化」
課題解決の第一歩は、各オウンドチャネルの推進部門にて、発生頻度の高いユースケースを抽出し、それらを「施策メニュー」として標準化することです。
具体的なプロセス
| # | プロセス | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | ユースケースの収集 | 過去にブランドチームから相談が多かったチャネル活用例や「やってみたい」施策をリストアップ。 例:Web講演会の事前告知・リマインドメール、製品サイトのSEO強化、特設ページ制作、クリックアンケート付きメール配信、リッチなCLMコンテンツ作成など。 |
| 2 | 施策メニュー化 |
収集したユースケースごとに、「この施策はこの流れ・この機能・この仕様で標準提供」と整理してパッケージ化。 例:「Web講演会告知メールパック」「製品キャンペーン特設ページ標準パック」「Survey連携CLMパック」など。 |
| 3 | “できることリスト”の可視化 | 施策メニューごとに利用可能な機能や成果物を明文化し、ブランドチームや社内関係者が一目で分かる資料やガイドラインを整備。 |
得られる効果
- ● 「どこまでできるか」が明確になり、施策立案や依頼がスムーズに
- ● 仕様調整や社内確認の手間が大幅に削減
- ● “パッケージ化”で、3rdPartyと同様の“気軽さ”を実現
オウンドチャネル活用の具体的な施策メニュー例
| カテゴリ | メニュー例 |
|---|---|
| オウンドサイト系 | ・製品キャンペーン用特設ページ制作 ・製品コンテンツ群のSEO対策 |
| メールキャンペーン系 |
・Web講演会向けメールパック(事前告知・リマインド・お礼) ・ターゲティングメール配信 ・クリックアンケート付きメール |
| Veeva CRM系 |
・リッチナビゲーション付きCLMコンテンツ ・Survey連携CLMコンテンツ ・Approved email用リッチテンプレート制作 |
2. 「標準費用」と「リードタイム」の明示で、予算・スケジュールの不安を払拭
現場のよくある課題
- ● 施策ごとの費用が分からない
- ● 予算申請や稟議の手間がかかる
- ● 準備期間(リードタイム)が読めず、依頼が遅れる
オウンドチャネル施策は個別対応になりがちで、費用や納期の見積もりが都度変動するため、ブランド担当者は予算申請やスケジュール調整に多くの時間を費やします。一方、3rdPartyはパッケージ価格や納期が明確なため、利用計画を立てやすいと評価されがちです。
解決策:「標準費用体系」と「リードタイム・役割分担表」の設定
施策メニューごとに
- ● 2~3種類の標準費用(例:スタンダード、カスタム、フルオプション)
- ● 必要なリードタイム(例:依頼から公開まで最短2週間、通常1か月など)
- ● 施策実施に必要な役割分担(依頼者、制作担当、法務・メディカルチェックなど)
を明示し、ブランド担当者が“見積もり不要”で施策を進められる仕組み作りが効果的です。
具体的なプロセス
| # | プロセス | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 施策メニューを作成し、価格と納期を設定 | 例:「Web講演会告知メールパック」XX万円/最短2週間など |
| 2 | トライアル施策実行 | 例:Web講演会のメール集客キャンペーン、特設ページ制作&SEO施策、CRMを活用したターゲティング配信など。 |
| 3 | 役割分担とスケジュールを“プレイブック”で提示 | 施策の流れ、各担当部門の役割、必要素材、社内審査のタイミング、費用感、期待効果などをまとめたプレイブックを作成。 |
| 4 | プレイブックの共有と説明会の実施 | ブランドチーム向けにプレイブックを配布し、説明会を実施 |
得られる効果
- ● 予算・スケジュールの不透明さが解消され、計画的な施策立案ができる
- ● 施策実施の工程や役割分担が明確になり、トラブルや手戻りが減少する
3. 「実践→検証→標準化」のサイクルで、現場に根付く仕組みを作る
現場のよくある課題
- ● 標準化しても利用されない
- ● 属人的、例外対応ばかりの施策
- ● 効果検証や改善が行われない
施策メニューやプレイブックを整備しても、現場のブランドチームが“自分ごと”として使いこなせなければ、活用は広まりません。また、初回施策でつまずくと「やはり3rdPartyでいいや」となり、オウンドチャネル利用の定着が進みません。
解決策:「トライアル→効果検証→標準化→全社展開」のサイクル化
まずユースケースごとに“トライアルチーム”を選定し、実際の施策を実施します。結果を効果検証し、課題点を洗い出してサービス仕様をブラッシュアップ。最終的にノウハウを全社で共有し標準化していくことが重要です。
具体的なプロセス
| # | プロセス | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | トライアルチームの選定 | 施策に積極的なブランドチームや新製品担当を選定し、実証実験を実施。 |
| 2 | トライアル施策実行 | 例:Web講演会のメール集客キャンペーン、特設ページ制作&SEO施策、CRMを活用したターゲティング配信など。 |
| 3 | 効果検証・フィードバック | KPI(開封率、クリック率、医師からの反応、サイト流入数など)を設定し、想定される期待成果を可視化。担当者から運用面での気づきや改善点もヒアリング。 |
| 4 | 仕様改善&標準化 | 現場の声をもとに施策メニューやプレイブックを改善。より実用的な標準仕様に昇華。 |
| 5 | 全社展開と教育施策 | ノウハウ・成功事例を全ブランドチームに共有し、活用事例共有会や勉強会で「オウンドチャネル活用文化」を根付かせる。 |
得られる効果
- ● 実際の現場課題を反映した“使える標準メニュー”が完成
- ● 担当者間でナレッジが共有され、属人化・例外対応が減少
- ● 効果の可視化により、「やって良かった」「また使いたい」というポジティブサイクルが生まれる
まとめ
オウンドチャネルは、もはや「コスト削減のための自社媒体」ではありません。医療従事者とのエンゲージメントを高め、他社との差別化を図る「戦略的資産」です。
製品ブランドチームがオウンドチャネルを積極的に活用するためには、
- ● できることの見える化(施策メニュー化)
- ● 標準費用・リードタイムの明示とプレイブックの整備
- ● トライアル・検証・標準化のサイクルによる現場定着
この3つのポイントを確実に押さえ、組織的なPDCAを回し続けることが不可欠です。
本記事が、貴社のデジタルマーケティング推進やブランドチームの“自走”促進の一助となれば幸いです。自社オウンドチャネルの可能性を最大化し、これからのオムニチャネルマーケティングを高度化させていきましょう。
MCI DIGITALではオウンドチャネル活用支援の一環として、製品ブランドチームに向けたプレイブックの整備も行っています。詳しくはこちら からお問い合わせください。
(担当:孫)
●合わせて読みたい記事