製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX クリニック院長編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
取材年月:2024年6月
医師は、製薬企業ウェブサイト(以下、製薬企業サイト)で、薬剤関連の情報をどのように収集しているのでしょうか?
本記事では、医師がいつ、どのような薬剤情報を収集しているのか、その際に製薬企業サイトをどのように活用しているのか、インタビューを通してご紹介します。
・診療科:皮膚科
・役職:院長
・年代:40代
・メディアマインドシェア:MR派
製薬企業ウェブサイトの役立ち度評価にポジティブに影響する情報である「薬剤の基本情報」と「実臨床で蓄積された情報」について、医師がどのような時に必要とし、どのように情報を収集するのかを明らかにするため、インタビューを行いました。
>>「インターネットチャネルごとの、「役立ち度」評価ポイント」(DM白書2024年夏号)
薬剤の基本情報を製薬企業サイトで確認する際の行動
薬剤の基本情報を調べるのは、どのような時でしょうか?具体的な調べ方と合わせて、Y先生に伺いました。
薬剤の基本情報を調べたいと思うのはどんな時ですか?
診察中に、処方している薬剤の詳細について、不明点が出てきた時です。具体的には、副作用、用法・用量、併用禁忌などで、ほとんどの場合、患者さんの目の前でPCを使って確認します。
具体的にどのように情報を探しますか?
Yahoo!で「製品名」に加えて、「服用回数」「適応」などの調べたいキーワードを組み合わせるか、「”製品名”+“添付文書”」と検索します。
検索結果の一覧から、実際に利用するサイトはどのように決めますか?
検索結果の上位から順番に確認します。信頼できる情報源と判断できれば、医療機関のウェブサイトを見ることもあります。
製薬企業サイトであるかどうかは重要視しますか?
いいえ。製薬企業サイトが最も正確な情報を得られるとは思いますが、他のサイトで目的の情報が得られれば十分です。
製薬企業サイトをご覧になった際、目的の情報は見つけられますか?
サイト内を探せば、添付文書を確認できます。ただ、製薬企業ごとにサイトの作りが異なるため、どこに何の情報があるのか迷うことがあります。
実臨床で蓄積されたデータを探す際の行動
実臨床で蓄積されたデータは、どのような時に必要となるのでしょうか?具体的な調べ方と合わせて、Y先生に伺いました。
実臨床で蓄積された情報はどのように収集されますか?
市販直後調査などの実臨床で蓄積されたデータは、自分から調べることはほとんどなくて、MRからの情報提供や、他施設の医師から情報を得ることが多いです。
患者さんの副作用発現状況に合わせて、実臨床で蓄積されたデータを確認することはありますか?
いいえ。副作用の発現割合は実臨床と乖離していることが多いので、患者さんの訴える症状が添付文書に記載されているかどうかを確認できれば十分です。
添付文書の情報で対応できるということでしょうか?
はい。添付文書の情報に加えて、過去の投与経験から、ある程度判断できます。
患者さんに重篤な副作用が発現したときなどで添付文書を見てもよくわからないときは、追加情報をどのように収集しますか?
すぐに確認できる医中誌など、インターネットで論文を調べます。
インターネットで調べる際、製薬企業サイトは利用されないのでしょうか。
先入観かもしれませんが、製薬企業サイトは売り込みたいというメッセージが強い印象で、個別の具体的な症例情報など論文で調べるような込み入った情報は掲載されていないと思います。
製薬企業サイトに個別症例や実臨床で蓄積された副作用情報が検索できるようなツールがあると利用しますか?
それはいいですね。個別症例の情報は貴重なので、製薬企業サイト上でそうした情報にスムーズにアクセスできるような工夫があれば、利用すると思います。
皮膚科領域における製薬企業サイトの評価
先生に、実際にPCを操作していただきながら、処方されている薬剤についてインターネット検索する際の流れや、製薬企業サイトの評価などを伺いました。
<製薬企業A 薬剤B>
薬剤Bについて検索してみてください。
Yahoo!で「“製品名B”+“薬剤情報”」と検索してみます。一番上に表示された「KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes(https://www.kegg.jp/)」へアクセスします。このサイトは検索結果でよく表示されるので使い慣れていて、添付文書はすぐに見つけられます。
添付文書が見つかりましたが、これ以上、他の情報を探すことはありますか?
いいえ。投与する上で必要な情報は確認できたため、これで十分です。
検索方法は「”薬剤名”+“薬剤情報”」というキーワードの組み合わせが多いのでしょうか?
はい。「薬剤名」単独で検索することはあまりなく、今回は無意識に「薬剤情報」と合わせて検索していました。
製薬企業Aのサイトで、薬剤Bのページを見ていただき、評価をお願いします。
薬剤Bは適応症も多く、画面上にたくさんの情報が掲載されていて、ごちゃごちゃしている印象です。また、画像やアイコンが少なく、文字ばかりなので読みづらいです。
薬剤Bの添付文書を探してみてください。
添付文書は、ページ上部に目立つ大きさで配置されていたのですぐに見つけることができました。他の製薬企業サイトでは、このようにすぐに見つけられないと思います。
製薬企業Aのサイトにアクセスする際、興味のある領域で「皮膚科」を選択されましたが、薬剤Bのページでは皮膚科領域の情報に絞り込まれていませんでした。情報が絞り込まれた方が使いやすいですか?
はい、使いやすいと思います。ただ、薬剤の適応症が、皮膚科関連以外にも多岐にわたる場合、それらの情報が同じページにまとまっていても構いません。薬剤に関する幅広い知識は診療時に役立つことがあるので。
ページ上部にある「おすすめコンテンツ」は確認しますか?
空き時間や休み時間など、1人で情報を探しているときは確認するかもしれません。
<製薬企業C 薬剤D>
続いて、薬剤Dについて調べてみてください。
「製品名D」だけで検索してみます。製薬企業Cの患者さん向けのサイトを見つけましたが、患者さん向けサイトでは臨床上の疑問点は解消できません。臨床上の疑問があるときに、患者さん向けのサイトが検索結果の上位に表示されると困りますね。改めて「製品名D +薬剤情報」で検索し、10番目くらいに表示された製薬企業Cの医療関係者向けサイトにアクセスします。
アクセスしたページは、薬剤Dの製品情報が掲載されたページですか?
はい。薬剤Dのビジュアルが大きく表示されているので、製品情報ページだと思います。
アクセスしたページで、添付文書の情報は見つけられそうですか?
いいえ。ページにアクセスすると、製品のビジュアルが目につき、添付文書は見当たりません。下にスクロールしたら添付文書がありましたが、アクセスしたページの上部ですぐに見つけられない場合は、時間がもったいないので、他のサイトで情報を探すと思います。
同じページに掲載されている薬剤Dの臨床試験の情報は確認しますか?
新薬発売時は確認しますが、処方開始後に見ることはほとんどありません。
<製薬企業E 薬剤F>
薬剤Fについて検索をお願いします
「製品名F」で検索して、上位に表示された「製品名F」と書かれたサイトにアクセスしてみましたが、患者さん向けのページでした。患者さん向けか医療者向けかは、検索結果からはすぐに判断できませんでした。検索結果をもう少し探したところ、製薬企業Eの医療関係者向けサイトを見つけました。
薬剤Fのページは薬剤Bのページのように、添付文書へのリンクがページの上部にありませんが、探しにくさは感じませんか?
探しにくさは感じません。薬剤Fでは、ページの冒頭に薬剤のビジュアルが表示され、添付文書へのリンクはありませんが、製品特性、製品基本情報に遷移できるボタンをすぐに発見できたので、「このページに必要な情報がありそうだ」と判断できました。
ページ内に薬剤のビジュアルが埋め込まれていることは、先生にとって意味がありますか?
あまり気にしていませんが、薬剤の印象を記憶しやすくする効果はあると思います。邪魔にならない大きさであれば、あっても良いのではないでしょうか。
ページ内にある薬剤に関連したコンテンツは閲覧されますか?
あまり見ません。ただ、体重や年齢で用量が変わる薬剤の用法用量を確認する早見表がサイトで見られると助かります。
添付文書を探す際に、薬剤に関連した動画も確認しますか?
添付文書を探すのは、ほとんどの場合診療中なので、動画を見ることはありません。
製薬企業サイトで動画を確認することはありますか?
動画は主にm3で視聴しているため、製薬企業サイトではあまり見ません。製薬企業Eは医療関係者向けサイトのメールマガジンに登録しており、新しい動画コンテンツの案内メールが送られてくると、それをきっかけに視聴することがあります。
<製薬企業G 薬剤H>
最後に、製薬企業Gのサイトで、薬剤Hのページの評価をお願いします。
ヘッダー部分に「基本情報」「作用機序」「臨床成績」といったボタンが目に付くように掲載されているので、調べたい情報にすぐたどり着けそうです。臨床上の疑問点を解消するという観点では、今回確認した製薬企業サイトの中で、薬剤Hのサイトが最も情報を探しやすいです。
添付文書の一部内容がPDFだけでなく、テキストでも掲載されていますが、どちらの方が使いやすいですか?
1回でもクリックする回数を減らしたいので、テキストで情報が表示されている方がありがたいです。
「よくある質問」というページを見ますか?
いいえ、見たことはありません。今回初めて見ましたが、調べたい内容がQ&A形式でまとまっていて、使いやすい印象です。
「よくある質問」は、どのように活用できそうですか?
臨床現場での疑問解消というよりは、事前に目を通して知識を深めておくために活用できそうです。
「よくある質問」を今後活用したいですか?
薬剤Hの「よくある質問」のように、情報がわかりやすくまとまっていれば活用したいです。ただ、製薬企業によってレイアウトや内容が異なるので、すべての「よくある質問」が活用できるとは限りません。
4サイトを通じての製薬企業サイト評価
製薬企業サイトでの情報収集についてどのように感じますか?
製薬企業ごとにサイトのレイアウトが異なるので、必要な情報が探しにくいと感じます。
製薬企業サイトにアクセスしたページで必要な情報がない場合、ヘッダーにある「製品情報」などのリンクから他のページを確認しますか?
時間がもったいないので、別のサイトで探します。最初にアクセスしたページで情報が得られるかどうかが重要です。
製薬企業サイトの使い勝手を良くするために、どのような点を改善してほしいですか?
製薬企業ごとにサイトのレイアウトが異なるため、目的の情報を調べるのに時間がかかります。どの製薬企業サイトでも、共通のレイアウトで情報が提供されると、迷わず情報を探せると思います。
患者さん向けの説明資料を、PC画面を通して患者さんに説明することはありますか?
基本的にはありません。MRが持ってきてくれる紙の資料を使って説明します。
製薬企業サイトで、添付文書の改訂情報を調べますか?
いいえ。MRが持参するか、製薬企業から手紙が届くので、そちらで確認します。
薬剤の剤形写真は必要ですか?
患者さんから、服用中の薬剤について錠剤の色や形で説明されることがあるので、薬剤のイメージを掴んでおくという観点では、剤形写真も有用だと思います。
製薬企業サイト内のチャットで相談できる機能は利用しますか?
1度も使ったことはありません。まずは自分で調べるので、使わなければならない事態になったことがないです。
ラボ編集部より
Y先生は、日常診療で生じた薬剤の疑問を解消するため、Yahoo! で検索を行い、検索結果の上位に表示された信頼できると思われるサイトで情報を確認し、目的の情報が得られないと感じた場合、すぐに他のサイトを再検索する傾向がありました。この情報収集プロセスは、過去にインタビューを行ったO先生と同様でした。
Y先生は、他の医師と同様に、製薬企業サイトは情報を探しにくいと感じており、特に製薬企業毎のレイアウトの違いが使いにくいと指摘しています。今回のインタビューでは薬剤の基本情報収集に焦点を当てましたが、Y先生のサイト利用時の行動や発言からは、各社が薬剤情報ページの掲載方法に工夫を凝らしているものの、それがかえって医師の薬剤情報収集におけるユーザー体験を損ねている可能性も垣間見えました。
医師は明確な目的を持って製薬企業サイトにアクセスする際、訪問動機となった情報がすぐに入手できないと、他のサイトへ移動してしまうと考えられます。この前提のもと、製薬企業サイトとして、どのようなユーザー体験を提供できるかを考慮し、SEO対策や流入したページの情報設計を検討していく必要があると考えられます。
今後明らかにしていくこと
3名の医師への製薬企業オウンドサイトでの情報収集についてのインタビューでは
・目的の情報を見つけられない
・情報が見づらい、読みづらい
といった声を伺いました。
では、医師の使いやすいサイトにするためにはどのような点に配慮すべきなのでしょうか。医師の求めるサイトとはどんなものなのか?を、引き続きインタビューを通して調査していきます。
●合わせて読みたい記事
-
 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 私立病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 私立病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
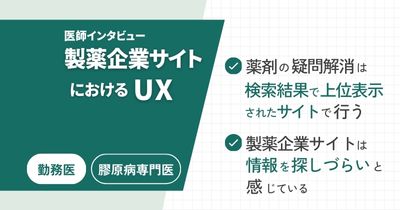 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 大学病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 大学病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
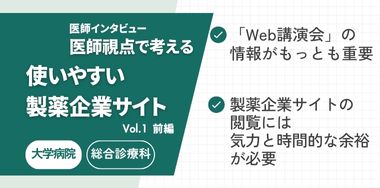 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
-
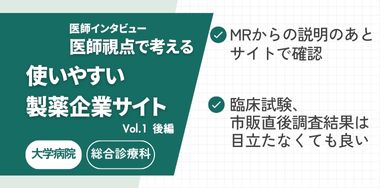 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
-
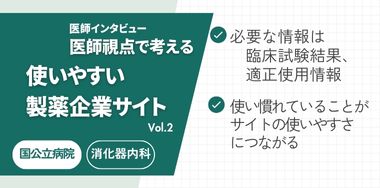 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
-
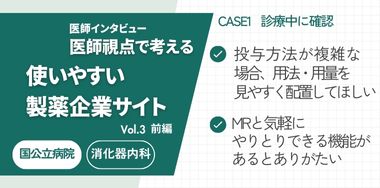 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
-
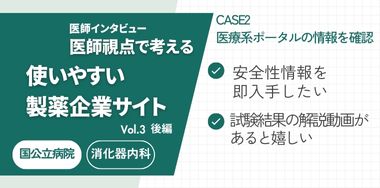 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
-
 製薬企業サイトが使いづらい理由No.1は「会員登録・ログインが手間」(63.5%)【DLあり】
製薬企業サイトが使いづらい理由No.1は「会員登録・ログインが手間」(63.5%)【DLあり】
 同じテーマの記事を見つける
同じテーマの記事を見つける
合わせて読みたい
-
定量調査
-
定性調査
-
事例
