製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 私立病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
取材年月:2024年5月
医師は、製薬企業ウェブサイト(以下、製薬企業サイト)上で、薬剤関連の情報をどのように収集しているのでしょうか?
本記事では、医師がいつ、どのような薬剤情報を収集しているのか、その際に製薬企業サイトをどのように活用しているのか、インタビューを通してご紹介します。
・診療科:精神科
・年代:40代
・メディアマインドシェア:MR派
製薬企業ウェブサイトの役立ち度評価にポジティブに影響する情報である「薬剤の基本情報」と「実臨床で蓄積された情報」について、医師がどのような時に必要とし、どのように情報を収集するのかを明らかにするため、インタビューを行いました。
>>「インターネットチャネルごとの、「役立ち度」評価ポイント」(DM白書2024年夏号)
薬剤の基本情報を製薬企業サイトで確認する際の行動
薬剤の基本情報を調べるのは、どのような時でしょうか?具体的な調べ方と合わせて、N先生に伺いました。
薬剤の基本情報はどんな時に調べますか?
薬剤処方時に、臨床上の疑問が生じたときや、患者さんに副作用が発生したときに薬剤基本情報を調べます。
診療中に疑問点を調べることもありますか?
多くの場合は診療時間外にインターネットサイトで調べます。精神科は他の診療科と比べて、治療や診察の時間が比較的ゆっくりと進むため、診療中にすぐ回答しなければならないケースは少ないからです。診療中であれば「今日の治療薬」などの書籍を利用します。
主にどのような情報を確認するのでしょうか?
副作用情報が多いですね。薬剤の飲み方や相互作用、薬剤の効果が食事の影響をどの程度受けるかなどを確認することもあります。
薬剤に関する基本情報を調べる手順を教えてください。
製薬企業サイトで調べます。まず、Yahoo!で「薬剤名 + DI」のように入力して、製薬企業サイトを探します。
薬剤基本情報は、製薬企業サイトで調べると決めているのですか?
はい。製薬企業サイトで掲載している情報が、最も信頼度が高いと判断しているためです。
検索結果に製薬企業サイトが表示されないこともありますか?
いいえ、ありません。専門領域の薬剤であれば、販売しているメーカー名がわかるので、「薬剤名 + DI」で見つからなくても、メーカー名で検索すれば見つかります。ただ、専門外の薬剤の場合は、メーカー名がわからないこともあるので、検索結果に表示された製薬企業以外のサイトを見ることもあります。
添付文書で掲載されている副作用情報を確認した後に、市販直後調査などのリアルワールドデータを調べることはありますか?
はい。副作用の発生状況など、添付文書に記載されている治験データだけでは不十分だと感じる場合は、市販直後調査などの結果を確認したり、MRに問い合わせたりすることもあります。ただし、最初から市販直後調査などの結果を調べることはあまりありません。
添付文書の情報だけで疑問点が解決しない場合、どうしますか?
医中誌で論文を探します。
医中誌は、それ以外にどのような時に利用しますか?
製薬企業サイトでは見つからないと思われる情報や、DIに載っていない情報は、最初から医中誌で論文を探します。
実臨床で蓄積されたデータを探す際のステージと行動
実臨床で蓄積されたデータは、どのような時に必要となるのでしょうか?具体的な調べ方と合わせて、N先生に伺いました。
実臨床で蓄積されたデータを探す際は、どのように探しますか?
インターネットで情報を探します。
製薬企業サイト、医中誌のどちらを利用されることが多いのでしょうか?
医中誌です。市販直後調査などの情報などは、製薬企業サイトで確認することはあります。
医中誌では、製薬企業サイトで載っていない情報を調べるために利用しているのでしょうか?
はい。実臨床で蓄積された症例報告などの情報を医中誌で確認しています。製薬企業サイトには症例に関する情報はあまり載っていないので。
精神科領域における製薬企業サイトの評価
先生に、実際にPCを操作していただきながら、処方されている薬剤についてインターネット検索する際の流れや、製薬企業サイトの評価などを伺いました。
<製薬企業A 薬剤B>
薬剤Bの情報を検索していただけますでしょうか
食事が薬剤Bに及ぼす影響を調べるために、Yahoo!で「薬剤B + DI」と入力してみます。製薬企業Aのサイトが表示されないので、「薬剤B + DI +
製薬企業A」で再検索してみます。製薬企業Aのサイトが見つかりました。
検索結果のリンクから薬剤Bのページに遷移し、ページ上では電子添付文書がすぐに見つかりました。添付文書の薬物動態の項目で食後と空腹時の血中濃度データを確認します。実臨床では食事をあまり摂らない患者さんもいるので、どの程度の量を食べればいいのかを確認したいのですが、添付文書には記載されていませんでした。薬剤Bのページに戻りざっと他のコンテンツも探しましたが、必要な情報は得られず、医中誌での検索に切り替えます。
すぐに医中誌に遷移されましたね
製薬企業サイトでこれ以上探しても、必要な情報は入手できないと判断したためです。
製薬企業サイトに添付文書だけでなく、市販直後調査などの関連情報のボタンがすぐ近くにある場合は確認すると思いますか?
確認します。必要な情報が纏まっていて、視認性が良いレイアウトだといいですね。
医中誌で検索の進め方を教えてください
医中誌では、「食欲不振 + 一般名」などで検索し、10回程度条件を変えても情報が見つからなければ諦めます。
薬剤Bは製薬企業サイトと医中誌の両方で検索されましたが、製薬企業サイトで薬剤Bに関する論文にアクセスできるとしたら便利ですか?
はい、非常に便利だと思います。海外の有名な論文のサマリなどがあれば、興味深く読ませていただきます。
製薬企業Aのサイトデザインについて、先生の感想を教えてください
製薬企業Aのサイトは画像付きでコンテンツが紹介されていて、情報も整理されており、見やすいので好印象です。
<製薬企業C 薬剤D>
続いて、薬剤Dについて検索をお願いします。
Yahoo!で「薬剤D + 添付文書」と検索しましたが、検索結果に製薬企業Cのサイトは表示されませんでした。そこで、企業名を追加して再検索しようやく見つけることができました。
薬剤Dの検索を続けてください
添付文書で、特定症状の副作用の割合を調べてみます。製薬企業Cは添付文書が見つけやすいです。添付文書の内容だけでは足りなかったのですが、添付文書の近くに市販後安全性情報のボタンがあるので、これは押してみようと思いますね。
さきほどの製薬企業Aのサイトには添付文書の近くに市販直後調査などのボタンがなかったので、市販直後調査などを追加で確認しようとはなりませんでした。
市販直後調査などのデータを最初から確認することはありますか?
ありません。はじめに添付文書を開くのが癖になっているので、まずは添付文書を確認します。
製薬企業Cのサイトデザインについて先生の感想を教えてください
テキストが多く画像なども少ないため、少し見づらい印象です。添付文書以外の情報が目につきにくく、追加の情報を探しづらいと感じます。また、過去の利用経験からも、製薬企業Cのサイトは印象が悪いです。
製薬企業Cのサイトの印象が悪いのはなぜでしょうか?
以前、医療系ポータルサイトから製薬企業Cのサイトに遷移しようとした際、ログインが必要で、すぐにコンテンツを閲覧できませんでした。興味を持った情報にアクセスできず、使いにくいと感じました。
<製薬企業E 薬剤F>
製薬企業Eの薬剤Fのサイトデザインについて評価をお願いします
薬剤情報が上部にあり、関連情報が画像付きで紹介されているので、理解しやすいと感じます。また、お役立ち情報や患者さん向けのツールなどもあって、情報も充実している印象です。
薬剤Fのページにある「お役立ち情報」ボタンは、押そうと思いますか?
押してみます。ただ、ログインIDとパスワードを求められた場合は、面倒なのでやめるかもしれません。
3サイトを通じての製薬企業サイト評価
添付文書を確認した際に興味を持ったコンテンツを、後から見返すことはありますか?
基本的にはありません。MRや医療系ポータルサイトで見たことのある情報が多いからです。ただし、コンテンツによっては、過去の情報提供を思い出すきっかけになることもあります。
動画を目的に製薬企業のサイトを利用することはありますか?
ありません。製薬企業のサイトではテキストベースの情報を収集して、動画はm3などのポイントが貯まる医療系ポータルサイトで耳学問的に視聴する程度です。
薬剤情報のページにある剤形写真は必要でしょうか?
あった方がいいと思いますが、サイズは大きくなくても構いません。剤形写真があると、薬剤の色や刻印を自然と覚えられ、患者さんとのコミュニケーションなどで役立つことがあります。
患者指導箋などの資材を製薬企業のサイトから注文されることはありますか?
専門領域の薬剤に関する資材はMRに直接注文するので、サイトからは利用しません。専門外の薬剤で担当MRがわからない場合は、サイトから注文したことがあるかもしれません。
論文の情報があると役に立ちますか?
薬剤Bのところでもお話ししたとおり、海外論文のサマリなどがあると非常に役に立ちますね。
添付文書はPDF以外の形式の方が、見やすいと思われますか?
PDFで特に問題ありません。
先生にとって、すぐに添付文書を見つけられる製薬企業サイトは使いやすいですか?
はい、使いやすいです。しかし、どの製薬企業サイトでも添付文書は見つけられるので、役に立ちそうなコンテンツが充実している製薬企業Aと製薬企業Eのサイトの方が好みです。
先生にとって役に立つコンテンツとは、どのようなものでしょうか?
薬剤の作用機序の解説、Q&A、患者さん向けの資材、海外の臨床試験データなど、製薬企業ならではの信頼性が高く、実用的な情報があれば役に立つと思います。
ラボ編集部より
3つの製薬企業サイトを、N先生に操作してもらいながら意見を聞いたところ、どのサイトもユーザーの訪問動機に合わせてサイトを最適化しているとは言い難い結果となりました。
N先生が日々の診療で抱える薬剤処方における疑問点を解消する際、まず確認するのが製薬企業サイトの添付文書とのことでした。添付文書で解決しない場合は、医中誌で論文検索など、より詳細な情報収集へと移行しますが、N先生は、製薬企業サイトに市販直後調査などのデータや論文サマリなどがあれば、積極的に活用する意向を示しています。
しかし、N先生にサイトを実際に操作していただいたところ、追加で収集したいと考える情報が見つけづらいという課題も浮き彫りになりました。
製薬企業は、医師が最初にアクセスする薬剤情報ページ上で、薬剤基本情報だけでなく、市販直後調査などのデータや論文サマリなどの「製薬企業だから持っている情報」を同一ページ内に配置するなどわかりやすく配置することで、医師が必要とする情報を的確に提供できるようになるでしょう。
これにより、医師は臨床における疑問点を迅速に解決できるようになり、製薬企業サイト上のユーザー体験を向上する要因の1つとなりそうです。
●合わせて読みたい記事
-
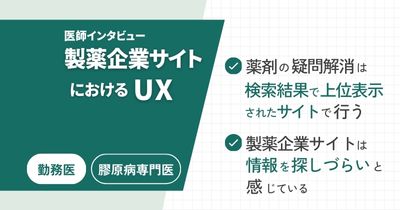 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 大学病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 大学病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
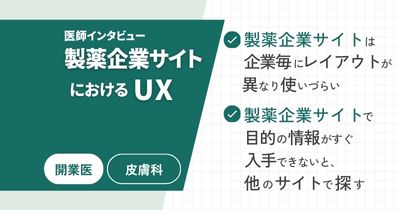 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX クリニック院長編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX クリニック院長編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
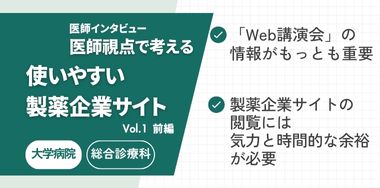 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
-
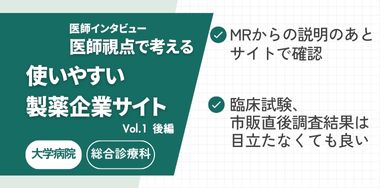 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
-
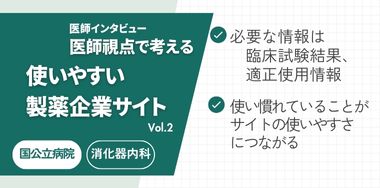 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
-
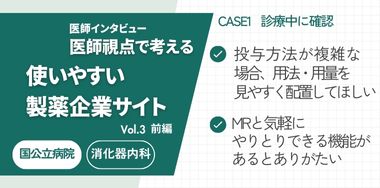 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
-
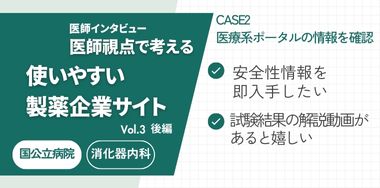 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
 同じテーマの記事を見つける
同じテーマの記事を見つける
合わせて読みたい
-
定量調査
-
定性調査
-
事例
