製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 大学病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
取材年月:2024年5月
医師は、製薬企業ウェブサイト(以下、製薬企業サイト)で、薬剤関連の情報をどのように収集しているのでしょうか?
本記事では、医師がいつ、どのような薬剤情報を収集しているのか、その際に製薬企業サイトをどのように活用しているのか、インタビューを通してご紹介します。
・診療科:総合診療科(膠原病専門)
・年代:40代
製薬企業ウェブサイトの役立ち度評価にポジティブに影響する情報である「薬剤の基本情報」と「実臨床で蓄積された情報」について、医師がどのような時に必要とし、どのように情報を収集するのかを明らかにするため、インタビューを行いました。
>>「インターネットチャネルごとの、「役立ち度」評価ポイント」(DM白書2024年夏号)
薬剤の基本情報を製薬企業サイトで確認する際の行動
薬剤の基本情報を調べるのは、どのような時でしょうか?具体的な調べ方と合わせて、O先生に伺いました。
薬剤の基本情報を調べるのはどんな時ですか?
外来での診察の合間が多いです。次の患者さんの処方検討時、薬剤の飲み合わせの確認などをしています。診察室のパソコンで患者さんと一緒に見ることもあります。
主にどのような情報を確認するのでしょうか?
薬価、副作用、併用禁忌の薬剤などを確認します。専門領域の薬剤は薬価が高いものもあるので、薬価によって処方を変えることもあります。
具体的にどのように調べるのか教えてください
インターネットで調べます。Yahoo!で「一般名」に加えて、「薬価」「副作用」「併用禁忌」などのキーワードを組み合わせて検索し、検索結果の上位から順番に確認します。ただし、クリニックや個人のブログなどは参考にしません。
検索結果として表示されたサイトが製薬企業サイトかどうかは気にしませんか?
はい、あまり気にしません。最初にアクセスしたサイトで目的の情報が見つかれば十分です。検索結果の2ページ目まで見ることはほとんどありません。
検索の際に製薬企業名は入力しませんか?
薬剤名と製薬企業名が結びつかないので、入力しません。
必要な情報が見つからないのはどのような場合でしょうか?
論文で確認すべきような詳細情報をインターネットで探したときですね。時間がないので手軽に情報収集したいという気持ちで検索しても、なかなか見つかりません。
検索後アクセスしたサイト内で情報を確認するときについて教えてください。具体的にどうやって情報を探しますか?
診療の合間など、時間がないときに調べるので、サイトをざっと見て、1ページ目をスクロールし、必要な情報が見つからなければ、すぐにあきらめて検索しなおします。
製薬企業サイトで必要な情報を見つけた場合、そのサイトの他の情報もご覧になりますか?
基本情報を確認したらすぐにサイトを閉じることが多いです。ただ、専門領域に近い内容で、著名な先生の解説動画などがあれば、時間があるときに見てみるかもしれません。
診療の合間など、短時間で情報収集する際に、どのようなコンテンツがあればご覧になりますか?
5分程度で薬剤の概要が理解できるような、短く簡潔なコンテンツであれば、見る機会が多いと思います。また、診療の合間など、手が離せない状況では、音声で確認できる動画コンテンツの方が便利です。
基本情報を検索する中で、面白そうだと思ったコンテンツを、後から見返すことはありますか?
はい。後で見たいと思ったコンテンツは、URLを自分のメールに送って保存しています。ブックマークだと管理しきれないので。
実臨床で蓄積されたデータを探す際の行動
実臨床で蓄積されたデータは、どのような時に必要となるのでしょうか?具体的な調べ方と合わせて、O先生に伺いました。
実臨床で蓄積されたデータを探すのはどのようなケースでしょうか?
専門領域の新薬が発売されたときです。発売直後は、臨床試験に関する論文に目を通して概要を理解します。その後、新薬の処方対象となる患者さんが来た際に、改めてインターネットで情報収集します。この時は、患者さんの治療方針を立てるために、まとまった時間を取って検索します。
実臨床で蓄積されたデータを探すのは、新薬が発売された後、実際に処方する前ということでしょうか?
はい、その通りです。私の勤務先は、膠原病の最先端と言えるほどではないので、他の施設の状況を参考にしながら、慎重に判断するようにしています。
実臨床で蓄積されたデータの具体的な調べ方を教えてください
「薬剤名」と「臨床試験」の2語、または、「市販後調査」を加えてインターネットで検索します。「薬価」や「副作用」といった言葉よりも、「市販後調査」や「臨床試験」などの用語の方が、製薬企業サイトにたどり着きやすい印象です。
市販直後調査などの情報をMRに聞くことはありますか?
わたしは昔から情報を自分で調べる習慣があるので、ほとんどありません。製薬企業サイトなどを調べてもまったく情報が見つからない場合に、MRに聞いたことがある程度です。
実臨床で蓄積されたデータを探しても、処方に関する疑問が解決しない場合は、どうされますか?
1つのサイトを徹底的に調べることはせず、検索結果で表示された3~4つのサイトを確認しても情報が見つからない場合は、PubMedやUpToDateなどで論文を確認します。
論文ではどのような情報を確認しますか?
個別の症例情報です。症例情報は、インターネットサイトよりも論文の方が解決できる可能性が高いと思います。
個別の症例情報を入手したい場合は、他にどのような方法で情報収集されますか?
同じ医局の先生に相談したり、実臨床に近い話題が取り上げられるインターネット講演会を視聴したりすることもあります。
市販直後調査などの掲載ページに、処方経験が豊富な先生のインターネット講演会の動画へのリンクがあれば、確認しますか?
はい、確認します。
膠原病治療薬に関する製薬企業サイトの評価
先生に、実際にPCを操作していただきながら、処方されている薬剤についてインターネット検索する際の流れや、製薬企業サイトの評価などを伺いました。
<製薬企業A 薬剤B>
薬剤Bの情報を検索していただけますか
最近、製薬企業Aの薬剤Bを処方している患者さんに下痢の副作用が出ていたので、「”薬剤B”+“副作用”」で検索してみます。一番上に表示された「KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and
Genomes(https://www.kegg.jp/)」にアクセスしましたが、文字が細かく、目的の情報も見つけられなかったので、すぐに諦めて別のサイトを探します。
Yahoo!の検索結果に戻り、次に表示された「日経メディカルオンライン」を見てみましたが、副作用の情報が羅列されているだけで、今回必要な情報は掲載されていないと感じました。
検索語句を「"薬剤B" + "製薬企業A"」に変更して再検索し、製薬企業Aのサイトにアクセスしました。まずは「よくある質問」を確認しましたが、求める情報は見つかりませんでした。次に添付文書を確認し、下痢の副作用に関する情報を見つけることができました。
最初によくある質問に遷移されていましたが、いつも同じように検索されますか?
はい。パソコン上で添付文書の細かい字を見ることが大変だと感じているため、よくある質問を見ることが多いかもしれません。今回は、同じような副作用の症例がないかを確認したかったためです。
先生は、よくある質問にはどのような情報が載っていると思われていますか?
安全性や飲み忘れ時の対処法など、患者さん向けの重要な情報が掲載されていると思っていましたが、製薬企業Aのサイトでは用法用量等の基本情報が掲載されており、わたしの求める情報とは異なっていました。
添付文書の掲載方式がPDFではありませんが、先生にとって使いやすいですか?
このサイトの添付文書は、ページ内に埋め込まれていて、文字が小さく、スクロールや拡大等の操作がしにくいため、目的の箇所を探すのに苦労しました。
薬剤Bの製品名を最初に入力されていましたが、一般名ではなく製品名の方が調べやすかったのでしょうか?
先ほどは一般名で検索すると言いましたが、無意識に製品名で検索していました。意識していませんでしたが、一般名か製品名かは、薬剤によって使い分けているのかもしれません。
検索していた中で、他に目に留まった情報はありましたか?
動画は目に留まりましたが、以前から使用している薬剤なので、新しい情報はないだろうと思い、今回は確認しませんでした。
<製薬企業C 薬剤D>
続いて、薬剤Dについて検索をお願いします
Yahoo!で「”薬剤D”+“製薬企業C”+“疾患名”」で検索します。検索結果の上部にスポンサー広告が表示されますが、医療関係者向けではないと判断し、飛ばします。薬剤Dの適正使用ガイドの情報が表示されたので、そちらを確認します。
Yahoo!での検索結果から適正使用ガイドのPDFを確認されましたが、こちらで疑問が解消した場合はこれ以上探すことはしませんか?
はい、そこで終了します。ただし、PDFはパソコンでの閲覧が難しいので、もっと見やすいサイトを探すことが多いですね。
PDFは印刷して確認しますか?
いいえ、印刷すると紙が溜まってしまうので、パソコンの画面上で見ます。
次に製薬企業Cのサイトについて評価をお願いします。製薬企業Cでは、添付文書の内容がテキスト形式でページに埋め込まれていますが、どのような印象ですか?
行間が広く、パッと見て内容が頭に入ってくるレイアウトなので、とても読みやすいと感じました。
製薬企業Cのサイトには市販直後調査などのPDFを掲載したページがありますが、こちらの評価はいかがでしょうか?
この情報は、今まで見つけられずにいたので、とても助かります。実際に自分が使用している薬剤の使い方が正しいのか、副作用はどの程度起こるのかを確認するためにも、市販直後調査などの情報は重要です。
製薬企業Cには副作用情報がまとまったコンテンツが掲載されていますが、気づきましたか?
いいえ、気づきませんでした。このような情報が製薬企業サイトから得られるなら、使いたいと思うかもしれません。
<製薬企業E 薬剤F>
薬剤Fの実臨床で蓄積されたデータを検索してください。
「“薬剤F”+“臨床試験”+“製薬企業E”」で検索します。検索結果の1番目には薬剤Fに関するプレスリリースが表示されますが、今回は確認しません。検索結果をスクロールすると、製薬企業Eの医療者向けのページを見つけたので確認します。薬剤Fのページにアクセスできましたが、市販直後調査などの実臨床で蓄積したデータは見当たりませんね。
市販直後調査などの情報はご覧いただいているページにはありませんが、このようなときはどうされますか?
他のページも探してみます。製薬企業Eのサイトでは見つかりませんね。
「薬剤F製品情報」と書かれているボタンを押すと市販直後調査などの情報があるかもしれません
本当ですね。ここにありました。製品情報というと添付文書しか出てこないと思っていました。
製薬企業Eのサイトデザインについて先生の感想を教えてください
薬剤Fのページは、座談会などの情報が目を引くように紹介されていたり、画像を使ってコンテンツが紹介されていたりと、興味を惹かれる情報が多く内容を確認したくなりました。
ラボ編集部より
O先生は、日々の診療で生じる薬剤の疑問を解消するため、Yahoo!検索で情報収集を行い、製薬企業サイトに限らず、検索結果の上位に表示された信頼できると思われるサイトを参考にしています。しかし、流入したページで目的の情報がすぐに見つからない場合や、ページ上の情報が読みづらい場合は、他のサイトへ移動してしまう傾向があります。
一方で、薬剤情報と同一ページ内で薬剤に関する追加情報(資材や動画など)がわかりやすく掲載されている場合は、視聴につながる可能性についても示唆されました。
製薬企業サイトにて薬剤の疑問を解消したいと考える医師のユーザー体験を向上させるためにも、医師が検索する製品名や一般名などのキーワードでのSEO対策に加え、流入したページにおいてもわかりやすい導線や文章を読みやすくするデザインなどのUIを考慮する必要があるでしょう。
今回のインタビューに限らず、多くの医師から「製薬企業サイトは情報を探しにくい」という声が聞かれるため、医師のユーザー体験を起点として、製薬企業サイトの改善に取り組んでいくべきではないでしょうか。
●合わせて読みたい記事
-
 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 私立病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX 私立病院 勤務医編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
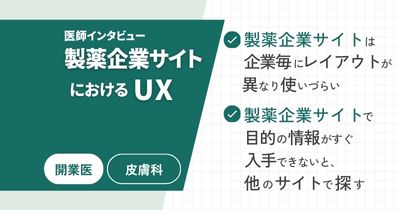 製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX クリニック院長編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
製薬企業オウンドサイトで薬剤情報を収集する医師のUX クリニック院長編│デジタルマーケティング担当者が知っておきたい医師の声
-
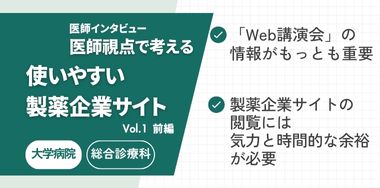 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 前編
-
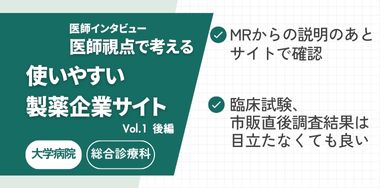 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.1 後編
-
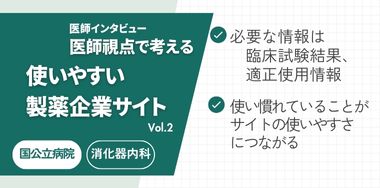 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.2
-
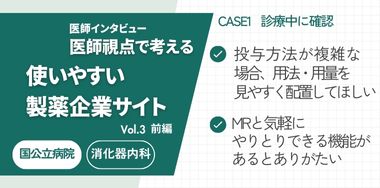 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 前編
-
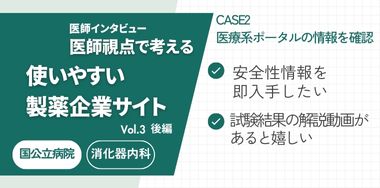 医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
医師視点で考える「使いやすい製薬企業オウンドサイト」 Vol.3 後編
 同じテーマの記事を見つける
同じテーマの記事を見つける
合わせて読みたい
-
定量調査
-
定性調査
-
事例
