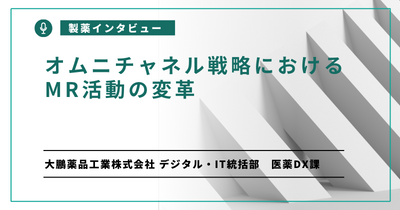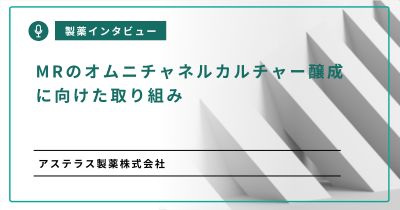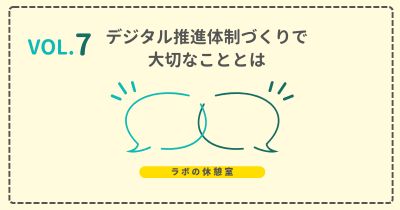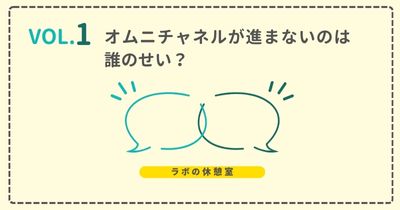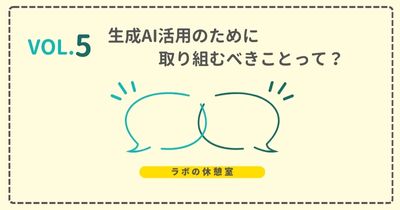ラボの休憩室 Vol.6 他部門は分かってくれない?マーケ・営業と共にデジタル推進をするために
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
取材年月 2025年8月
某製薬企業のDx推進担当。20年以上にわたり、ヘルスケア業界で営業、マーケティング、IT、Dxの多分野に従事。これまでの経験を通じて、普段感じていることを飾らずにお話いただきます。 ■千葉 理洋(仮名)
DM白書ラボ フェロー
目次
社内理解を得るために取り組むべきたった1つのこと
| 千葉氏 | デジタル推進って、他部門の理解がうまく得られずになかなか進まないという話をよく伺います。社内理解を得るために必要な取り組みってどんなことだと思われますか? |
|---|---|
| アリキキ氏 | これは結構シンプルで、社内で事例を作るということに尽きると考えています。まずは製品チーム、プロマネと一緒に効果検証を行って事例を1つ1つ作ります。これは「絶対やらなきゃいけないこと」です。ここをやらなければ他の部門を巻き込んだトライアル、施策の定着という流れを作れない。 |
| 千葉氏 | やはり社内事例なんですね。 |
| アリキキ氏 | 取り組みの中で、ここは改善した方がいいですねとか、この製品のバックグラウンドだとこのアクションプランがはまったのでそれをモディファイして他の製品チームでもやりませんか?という話ができる。 |
| 千葉氏 | 確かに大事ですね。 |
| アリキキ氏 | 結局、トライアンドエラーしていく文化を社内に作って定着させていかなきゃいけないと思っています。 |
マーケティング部門と共に推進する
| 千葉氏 | デジタル施策を一緒にやりやすいブランドと、そうではないブランドというのはありますか? |
|---|---|
| アリキキ氏 |
コミュニケーションがとれるプロマネはやりやすいです。「何とかしなきゃいけない」、「一緒に作っていきたい」と、ディスカッションを繰り返して落としどころを一緒に見つけてくれるプロマネはやりやすい。 でも、「いや、自分はこういうふうにやりたいから」って意固地なプロマネはやりづらいです。 |
| 千葉氏 | ブレない軸があるのはいいことですけど、話し合える柔軟さがあるといいですよね。 |
| アリキキ氏 | 追い込まれてる製品は、製品ポジショニングの問題もあるし、今までの売り方、アプローチ方法に課題があった、というケースもあります。そこを理解できていると前に進みやすい。そういう意味では、このブランドだからやりやすい、やりづらい、というのはないかもしれないです。 |
予算で揉めないためには、前年度からの合意が必要
| 千葉氏 | 事例を最初に作る時、どこがお金を出すか、という点が問題になることはないですか? |
|---|---|
| アリキキ氏 |
マーケが次年度のプランを作るときには入るようにしています。 「来年こういう取り組みするなら、こういうことにチャレンジしてみませんか?デジタル側でも予算申請しますから」と声をかけたりして、前年度からマーケチームと握っていますね。 |
| 千葉氏 | マーケティング戦略を作る段階で合意を得ておくんですね。 |
| アリキキ氏 |
はい。予算については折半のときもありますし、全額デジタルで負担する形で申請することもあります。 マーケティング戦略が決まってしまったあとに、新しい事例作りに合意してもらうのは難しいですよね。「今回m3への出稿で予算申請しています」というブランドに「他のチャネルの良さを生かしたいからm3以外のチャネルでやりませんか?」と後から言っても「なんで?」ってなってしまう。前年度に検討される戦略・戦術部分から入っていくっていうのは必須事項だと思います。 |
| 千葉氏 | なるほど。 |
デジタル×MRのハードルを乗り越えるために必要なこと
| 千葉氏 | ここまで対マーケ部門のお話を伺いましたが、対営業についてはどうでしょうか。例えば新たなツールや医師向けサービスを作って、MRに「使ってください」「先生に案内してください」と案内しても、営業側が思うように動いてくれないことって多いと思うんです。関係部門の理解を得ていくために必要なのはどんなことなんでしょうか。 |
|---|---|
| アリキキ氏 | 難しい質問をしますね(笑) |
| 千葉氏 | ぜひアリキキさんのご意見を伺いたいです(笑) |
| アリキキ氏 | 例えば会員制のオウンドサイトを作って、先生方の許諾を取るためのシステムを作って、MRさんにこのシステム使って許諾とってください、みたいな。 |
| 千葉氏 | よくあるケースですね。 |
| アリキキ氏 | まず誰もやりたがらないですよね。許諾件数をインセンティブにして何とかやってもらうみたいな…。でもMRさんのホンネとしてはやりたくないよね。だってMRさんのMR活動に見返りがない。 |
| 千葉氏 | …。 |
| アリキキ氏 | 「デジタルを活用することでこんなふうに効率化できる、だから率先して自分もデジタルを使おう」、っていうところまで落とし込まれてないから。本当は、MRさん側のメリット、支店長側のメリットを全面的に出していかなきゃいけない。でも本社側は「この情報収集してきて」と依頼はするけど、集められた情報に対するフィードバックをしない。価値を返していない。 |
| 千葉氏 | 確かにそういうケースは多いですね。 |
| アリキキ氏 | だから、わたしはできる限りMRさんに価値を感じてもらえるサービス設計を心がけています。MRさんは“この施策で自分に見返りがある”って実感できないと絶対に積極的に動かない。その価値を提供できないなら、インセンティブをつけるしかないっていう。ただ、業務命令でも見返りがなければやりたくないのが人情ですよね。 |
| 千葉氏 | まずはMRさんのメリットをしっかり伝えていく、ということですね。 |
| アリキキ氏 | 情報収集することで、MRさんへこういう情報をプラスアルファで提供されますというポジティブな情報を伝えておくことが必要です。MRさんにとっての価値を伝えきることができないなら、「こういう会社の事情があって、申し訳ないけどこういう協力をしてください」と、割り切って伝えるしかないと思っています。 |
| 千葉氏 | はい。 |
| アリキキ氏 | 患者さんの症例情報を収集するツールを作ってMRさんに情報収集してもらったりすることがあるじゃないですか。でも結局集めたデータがその後どう使われ、MRさんにどんな価値が生まれるのかはよくわからなかったりします。収集したけど何?…みたいな。 |
| 千葉氏 | そういうことは多いですよね。なんか「データがいっぱいあるといい」みたいな感覚。 |
| アリキキ氏 | いっぱいあっても、ただのデータなんですよね。 |
| 千葉氏 | 「データを集めておけばきっと何かできる…。」 |
| アリキキ氏 | 「きっと何かできる」っていうのは、「永久に何も生まれない」のと同じことです。 |
| 千葉氏 | 本来は「この目的のために、こういうデータが必要だ」っていうスタンスであるべきですよね。 |
| アリキキ氏 | そう。目的もなくまんべんなくデータ集めても、何も生まれないです。 |
定着させるためのキーパーソンは「2人目」
| アリキキ氏 | 社内理解を得るための取り組みとしては、社内への定着させるための仕組みを考えることも大切だと思っています。 |
|---|---|
| 千葉氏 | 具体的にどんなことでしょうか。 |
| アリキキ氏 | 例えば、まず管理職に限定して利用を定着させてから全社展開したり。 |
| 千葉氏 | 声の大きい人を最初に巻き込むということですね。 |
| アリキキ氏 | また、全員の理解を得られるのがベストですが、時間がかかりすぎてしまう場合には理解のない人は置いていく、ということも必要だと思います。 |
| 千葉氏 | それでいいのかもしれないですね。みんなが集まっていたらついていく、ということもあるし。いわゆるバンドワゴン効果※1ですね。 |
| アリキキ氏 | そう。気づいたら一緒に向かってた、という形に持って行った方が適度なスピードで推進していけるかなと思っています。 |
| 千葉氏 | その話で思い出したのが、「2人目が大事」といMDアンダーソンにいらした上野直人先生※2が講演で紹介されていた「裸の男とリーダーシップ」という動画です。動画では、はじめは裸の男性が1人で踊っているんですが、それを見ていた1人の男が突然一緒に踊り出すんです。そうしたら3人目、4人目、5人目が続いて踊り出したんです。最初にイノベーティブ的なことをやる人は1人いて、それに乗る2人目がいると3人目4人目5人目っていうのが勝手に現れるという。 |
| アリキキ氏 | 確かに「2人目」は大事ですね。 |
| 千葉氏 | 社内理解という文脈でも、最初から理解してくれる人はもちろん大事ですが、「2人目」に当たる、次についてきてくれる人をどう巻き込んでいくかというのは大事だと思いました。 |
| アリキキ氏 | 「2人目」をうまく作り、巻きこんでいけば、うまくハマっていくと思います。 |
- ※1 多くの人が支持しているものに対して追随すべきと思いこむ認知バイアスのこと。
- ※2 2025年現在はハワイ大学がんセンターがんセンター長
本記事へのご意見・ご感想はアンケート欄よりお寄せください。本コーナーに匿名で登場いただける方も募集中です!
次回は、ラボの休憩室 Vol.7 デジタル推進体制づくりで大切なこととは をお話しします。
(文:松原)