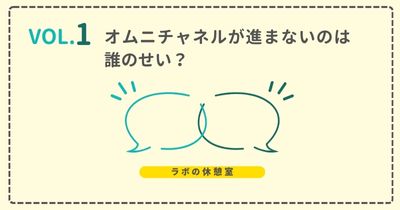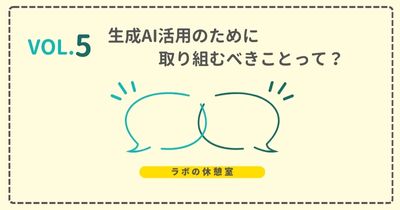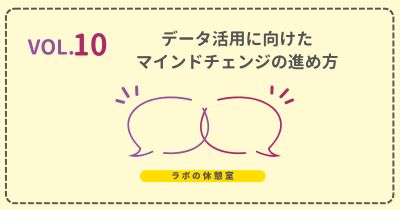ラボの休憩室 Vol.9 データドリブンで最適解を見つけるために必要なことは?
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
取材年月 2025年9月
大手製薬企業、外資系製薬企業にてMRを10年以上経験後、営業部門(MR、マネージャー)の人材育成の担当者としてソフトスキル・オムニチャネルトレーニング、ローンチ時の研修に5年間従事、その後、DX推進者として、本社間、本社-MR間のコミュニケーションのハブとなってプロジェクトマネジメント、チェンジマネジメントを担当。 ■千葉 理洋(仮名)
DM白書ラボ フェロー
| 千葉氏 | 今回は、製薬業界のDX推進者として、本社間、本社-MR間のコミュニケーションのハブとなってプロジェクトマネジメント、チェンジマネジメントを担当され、営業部門の人材開発の経験も豊富なセーダスさんにお話を伺います。よろしくお願いします。 |
|---|---|
| セーダス氏 | よろしくお願いします。 |
データ利活用の環境をどう作るか?
| 千葉氏 |
今日はデータの利活用のための理想と現状、そしてそれをどう埋めていけばいいのか?についてお話をうかがいたいです。 まず、データ利活用の理想的な環境ってどうあるべきでしょうか。 |
|---|---|
| セーダス氏 | データの構造化、非構造化に関わらず、すべてのデータが一元管理されていて、そこから必要に応じてデータを定型であれ非定型であれ活用できる状態であることが理想です。 |
| 千葉氏 | それって単純なことのように思えるのですが、そうではないのでしょうか。 |
| セーダス氏 |
実際はそう単純ではありません。 現状の課題は大きく2つあって、まず1つ目はマーケ部門、営業部門などの各部門が、自部門にとって必要なデータを取得できる環境整備を優先しているという点です。会社としてのデータレイク※1よりも、各部門が必要なデータを取得できるようにするためのデータウェアハウス※2を作っているような状態です。 2つ目は、各部門が独自に外部データを購入しているケースが多く、会社としてどんなデータがあり、どこに蓄積されているのかがわからないことです。こういったデータが半分以上はあるように思います。 |
- ※1 すべての構造化データと非構造化データを保存できる一元化されたリポジトリ。データをそのままの形で保存できるため、データを構造化しておく必要がない。
- ※2 複数のシステムに分散しているデータを集約・統合し、分析やレポート作成に最適化された形式で蓄積・管理するためのデータベースシステム。
ゴールを達成するためにデータを分析できていますか?
| 千葉氏 | なるほど。では、データ利活用のための理想的な体制についてはどのようにお考えですか? |
|---|---|
| セーダス氏 |
一番大切なのは「会社のゴールを各事業部が同じ目線で理解できている」ことだと考えています。
データって、ゴールを達成するために必要なものですよね。 大前提として会社の戦略があり、そこから降りてきた製品戦略があり、製品戦略に基づいた年間のゴールがあり、ゴールを達成するためのKGI、KPIが設定されています。これらの指標を、会社全体を見ている部門、事業部、各部門が同じ粒度で戦略を理解してデータを見ることができれば良いと思います。 |
| 千葉氏 | それって、例えばKGI、KPIをトラッキングするための会社としてのフレームワークがあり、それを各事業部が状況に応じてモディファイして使う、といったイメージでしょうか。 |
| セーダス氏 | はい。加えて、製品戦略についてはライフサイクル毎のフレームワークを用意する必要もあります。一方、チャネルミックスは共通のフレームワークがあります。戦略によって各チャネルの重み付けは変わりますが、基本的には共通のフレームワークを利用して分析しようというやり方が徐々に浸透してきています。 |
何のためのデータ分析?
| 千葉氏 | 全社で分析用の共通フォーマットを利用する場合、すべての部門にそのやり方を理解してもらい、徹底するというのはなかなか難しいのではないかと思うのですが、そのあたりはいかがでしょうか。とくにマーケ部門はやりたいことが明確なので、反発もあるのではないでしょうか。 |
|---|---|
| セーダス氏 | 弊社はデータ分析を事業部の外の部門で行っているので、事業部の恣意的な分析はしづらくなっています。以前は事業部側が戦略を立て、効果測定も行っていました。ですが、弊社は人のサイクルが早くてだいたい2~3年なんです。そうすると「ゴールを達成するための効果測定」ではなく、「自分たちの戦略が確からしい、良かった」というデータをだしてくるようになってしまうんです。 |
| 千葉氏 | あぁなるほど。 |
| セーダス氏 |
現在は、基本的には戦略に合わせてこちらが分析を行っています。とはいえ、分析ミスがないわけでなはなく、事業部の外で行っている分厳しい指摘も入ります。 この点については、データ分析側がどれだけプロになれるのか?だと思っています。戦略を立てて実行するのが戦略立案のプロなら、データ分析側は会社の方向性だけではなく戦略も理解し、戦略に基づいた客観的なデータ分析を行うプロであるという自負とケイパビリティを身に着ける必要があります。 戦略立案側と、データ分析側の相互関係、相互尊重が重要だと考えています。 |
| 千葉氏 | 事業部外の方が分析する場合に、恣意的な操作ができないだけに効果検証の結果が厳しいものになることも往々にしてあると思いますが、その点上層部は理解されているのでしょうか。 |
| セーダス氏 |
はい。本社から営業まですべて同じ指標で見ているものに関しては、効果検証して次の戦略に生かすという話ができています。 ただ、フォーキャストとバジェットについては、日本のトップとグローバルで握っている数字があり、日本国内で追っているものと違うっていうことは……大きな声では言えませんが、あります(笑) 結局のところ、データ分析によってみんなのモチベーションが上がり、患者さんにお薬を届ける、企業の成長のための戦略である、というゴールにつなげることができればいいんじゃないかと思っています。理想論ですけどね。 |
| 千葉氏 | 理想論、大事だと思います。 |
BIツールを活用したデータ分析へ
| 千葉氏 | データ分析にはトラッキング的なものと、機会やインサイトを見つけるためのものがあると思います。本社と事業部では分担しているのでしょうか? |
|---|---|
| セーダス氏 | 進捗管理的なトラッキングは、事業部側の営業推進的な部門が見ています。一方、効果測定や機会創出のための分析、インサイトの発見は本社側が見る、という棲み分けなんですが、それが正しいかどうかは議論の余地があると思っています。 |
| 千葉氏 | それはどうしてですか? |
| セーダス氏 | 事業部側がトラッキングを行うことによって、冒頭でお伝えしたトラッキング用のデータがどこにあるか分からないという状態を生み出しています。全社共通のデータ基盤を整え、そこからBIツールなりでトラッキングすればいいと思うんです。何をトラッキングすべきかを含め、本社と事業部で議論が始まりつつあり、事業部が独自で実施しているトラッキングは止める方向に話は進んでいます。 |
データ vs KKDの論争からは何も生まれない
| 千葉氏 |
インサイトを見出すという部分については、データから想定できる部分があるのと同時に、実際に医師と面談している現場からの経験値、KKD※3が強い、という側面もありますよね?このあたりはどうお考えですか? 例えば、ある企業で、機械の故障修理時にAIで解決方法を出すようにしたら、勘と経験で解決方法を3つまではだせるけど、AIがそれ以外の解決方法をサジェストしてくれて、故障の解決をしやすくなったという事例を聞いたことがあります。勘と経験だけでは足らない部分をデータが補うことで、「どちらか」という排他的な考え方ではなく、「両者を併せる」ことで、相乗効果を生み出せるのではないでしょうか。 |
|---|---|
| セーダス氏 | 始まりはデータでも勘と経験でも良くて、互いに受け入れることって大事だと思います。 |
| 千葉氏 | とはいえ、データサイエンティスト側も、現場のセールス側も、どちらも「自分たちが正しい」と主張しがちですよね。 |
| セーダス氏 | データを見ている側は、「もっと深堀したいから現場の経験と勘を知りたい」というマインドセットを持つべきだし、現場で経験値を持つ側は、データから確からしい情報を受け取ったときにまずそれを受け入れて考えてみる、というマインドセット持つべきなんです。このマインドセットを互いに持てれば、みんなでよりよい最適解を見つけることができると思います。 |
| 千葉氏 | 確かに互いに正しさを主張し合っても、そこからは何も生まれないですね。 |
| セーダス氏 | データドリブンに進めることは大切ですが、「データが正解」「経験が正解」というふうにどっちが正しいのか? という議論にならないようにしたくて、そこはお互いの力を借りようよ、っていうマインドセットを持ちたいし、それに尽きるかなと思います。どんなプロセスを踏むとしても、相互理解、相互尊重の先にしか求める正解はないと思うんです。 |
| 千葉氏 | たしかに、みんながそのマインドセットを持てれば、集合知として強いパワーを持てますよね。 |
- ※3 「経験(Keiken)、勘(Kan)、度胸(Dokyo)」
次回は、ラボの休憩室 Vol.10 データ活用に向けたマインドチェンジの進め方 をお話しします。
(文:松原)