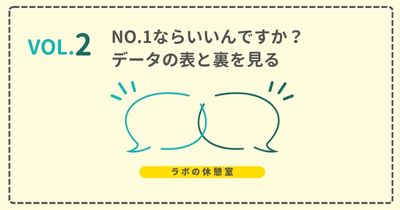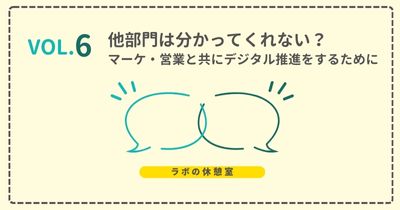ラボの休憩室 Vol.1 オムニチャネルが進まないのは誰のせい?
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
某製薬企業のDx推進担当。20年以上にわたり、ヘルスケア業界で営業、マーケティング、IT、Dxの多分野に従事。これまでの経験を通じて、普段感じていることを飾らずにお話いただきます。 ■千葉 理洋(仮名)
DM白書ラボ フェロー。
目次
オムニチャネルって?
| 千葉氏 | 今回は、製薬業界の方にいろんな視点でお話を伺うということで、業界経験の豊富なアリキキさんに来ていただきました。よろしくお願いします。 |
|---|---|
| アリキキ氏 | よろしくお願いします。いつも通りの感じでよいですか? |
| 千葉氏 | 記事になるので、いつもよりマイルドにお願いします(汗)そういえば、アリキキさんって、業界経験はどのくらいになるのでしたっけ? |
| アリキキ氏 | 複数の製薬企業勤務の経験があって、かれこれ20年以上この業界で働いていますね。 |
| 千葉氏 | 20年以上!そんなアリキキさんから色々とお伺いできればと思うのですが、今回はアリキキさんの興味のあるテーマでお話を進められればと思いますが、どんなテーマがよいですかね? |
| アリキキ氏 |
そうですね。やっぱりオムニチャネルじゃないですか?みんな大好きなキーワードじゃない? 移動中にワーってスマホで情報収集している人もいれば、僕みたいに移動中は寝てて、家に帰ってからPCで調べる人もいる。同じ情報を集めるにしてもチャネルの使い方って人によってバラバラですよね。どのチャネルからでも同じ情報が取れますよって、今の時代では大事ですよね。 |
| 千葉氏 |
たしかに。ではオムニチャネルでお願いします。 このオムニチャネルって、10年くらい業界のキーワードにはなっていますが、実際変わってきていると思いますか? |
| アリキキ氏 | あまり変わってないんじゃないかなぁ。 |
| 千葉氏 | うーん、確かにそうかもしれません。それって、何が理由なんでしょうか。 |
製薬業界でオムニチャネルが進まない理由って?
| アリキキ氏 | いろんな要因があると思いますよ。担当者、組織、経営層含めた上層部それぞれにあると思います。 |
|---|---|
| 千葉氏 | そうなんですね。では、担当者の要因とはどんなものでしょうか? |
| アリキキ氏 | やみくもに数を追ってしまうということが大きいですね。例えばデジタルで言えば、PVで1番を目指すとか。分かりやすい目標ではありますけど、その先に何があるの?っていう。 |
| 千葉氏 | なるほど。数に追われて本質からずれてしまっているということですかね。 |
| アリキキ氏 | そうなんです。本当に追わないといけないのは中身でしょう。本当に価値のある1,000PVなのか、ただただ訪れた10,000PVなのかは意味が違いますよね。 |
「これで売り上げにどのくらい貢献できますか?」
| アリキキ氏 | あと、やっぱりデジタルに期待されることとして「これで売り上げにどのくらい貢献できますか?」があります。これは毎回言う人がいますね。 |
|---|---|
| 千葉氏 | たしかによく聞く話ですね。 |
| アリキキ氏 | そのときに、「デジタルでできることはこういうことです」とはっきり伝える。 ここを曖昧にしてしまうと社内でのデジタルのポジションがグダグダになっちゃいます。 |
| 千葉氏 | たしかに。白書ラボで医師インタビューを数多く実施していますが、オウンドサイトってプル型の情報収集で利用している先生が圧倒的に多いんですよね。ですので、この、“自ら興味を持ってアクセスした”という貴重なデータをいかに活用するかが大事だと思うのですが、数に追われると、メールマガジンを増やしたりして数を稼ごうとしてしまう。アクセス数を増やすこと自体は悪いことではないのですが、自ら興味を持ってアクセスしたデータと、プッシュによってアクセスしたデータは色分けが必要かなと。プル型のオウンドサイトとプッシュ型の3rdPartyは数で比較するものではないですが、こういったチャネルごとの役割について社内で合意を作れていないと、両チャネルを数で比較してしまうので。 |
| アリキキ氏 | そうそう。ほんとに見なきゃいけないのは、医師にとって最適な情報提供は何?どうしたらいい?ということ。そのためには、ただの数値を目標値としないこと。これが一番肝心だと思います。 |
会社はほんとに腹くくってオムニチャネル実現しようと思ってますか?
| 千葉氏 | デジタルに関しての期待値コントロールがあまりされてないなっていうのも感じることがあります。3rdPartyでできることってこのぐらいだよね、オウンドサイトでできることってこのぐらいだよね。その中でどう使うかっていう。最近ではAIとかマーケティング・オートメーションもそうですけど。デジタルに詳しくないと、本来の期待効果以上の期待を持ってチャネルを見てしまいがちかなと。で、期待値コントロールができなくて高い成果を求められ、結果を出せないっていうことが起きてしまっているのかなと。 |
|---|---|
| アリキキ氏 |
実は、その期待に応えることは可能なんですよ。ただ、予算とリソースっていう制限がありますよね。結局予算とリソースの投下が継続できなくて道半ばで終わっちゃう。 継続してやるっていうことをやらない企業が多いですよね、初めにワーってやるんですけど。まあ3年くらい見ますよといってくれる会社もありますけど……。 会社はほんとに腹くくってオムニチャネル実現しようと思ってますか?っていうのはいつも思います。オムニチャネルは安くないし、ある程度お金も時間もかかりますって言ってるよね?って。 |
デジタルは安くて早い!?
| 千葉氏 | オムニチャネルって、まず1つ1つのチャネルをしっかり作り上げて、次にそのチャネルを組み合わせられる状態を作り上げて、そしてそれを活用できる人を育てる、といった段階を積み重ねていく必要があるので相当時間もかかるし、コストもかかりますよね。 |
|---|---|
| アリキキ氏 | そうなんですけどね。都合のいいときだけデジタルって安いよね、早いよね、みたいな牛丼みたいなことを言い始める。今や牛丼も安くはなくなったけどね(笑) |
| 千葉氏 | そういう愚痴を聞くことは結構多いですね(笑) |
| アリキキ氏 |
デジタルだからコンテンツも安いんじゃないの?っていうのは何回も聞いたし、変なプレッシャーの中でやらなきゃいけないみたいな。 でもそこは正しくちゃんと理解してもらわなきゃいけない。理解してもらって3年なら3年、5年なら5年かけてこういう結果を出していきます、そのためにマイルストーンを引いて、上に対して提案するっていうことを担当者はちゃんとやらなきゃいけない。上に理解してもらって、そこに予算をつけると。 ある程度コミットしておかないと、いざ1個1個のチャネルがモノになり始めました、じゃあ次のステップに進もうか、ってなったときに予算を外されました終了です、ということになってしまう。 |
現場だけではオムニチャネルは推進できない
| アリキキ氏 | 白書のデータでも、昔は役立ち度が高かったけど今は下がってきている企業ってありますよね。 |
|---|---|
| 千葉氏 |
はい。継続するってなかなか難しいんですね。少し話は逸れますが、オムニチャネルって企業のブランド力も影響すると思っています。この領域ならこの製薬企業だろう、みたいな。そういう状態を作り上げられていると、新しいチャネルを作ろうが何しようが、先生にすんなり使ってもらえるんですよね。 例えば、今話している部屋のモニターを例にとると、長年モニターを専門に作っている、とある国内メーカーが新製品の発売を発表した時と、アップルが発表した時とでは、どちらの期待度が高いですか? |
| アリキキ氏 | あー、もうこれは言わずもがなですね(笑)わくわく感が違います。 |
| 千葉氏 | ですよね。そういった状況を作り上げるためには、中長期的に本気でこの領域を極めますっていう全社方針が必要だと思います。今ちょっといい薬があるからやってます、だとその域にはいかない。 |
| アリキキ氏 | そういう会社は増えてくるんじゃないかな?実際、そういう企業の成功例を聞いたことがありますし。 |
| 千葉氏 | 私も聞いたことがあります。しっかりお金と時間かけて、コマーシャル戦略もいろいろやりながらメッセージを発信し続けてじわじわと、みたいな。これって、アリキキさんの言っていた、会社として腹をくくってコストと時間をかけてオムニチャネルを実現していくべきってことと一緒ですね。 |
| アリキキ氏 | そうですね。その過程って大切ですよね。うん。1年ぐらいで結果を求められるって、なかなかやっぱり大変です。そのプレッシャーっていうのはなかなかだし。そこは上層部にも現実路線で考えてほしい。 |
| 千葉氏 | オムニチャネルって、デジタルが出てきたあとに言われ始めたので、オムニチャネルはデジタル部門が担当するケースが多いんですけど、本来はそうではないと思っています。チャネルはデジタルだけじゃなくて、紙資材もあればリアル全国講演会もある。いろんなチャネルを使って、医師にどう最適な情報を提供するか?を考える部門が必要だと思います。 |
| アリキキ氏 | そういう会社さんも増えてきてはいますよね。各チャネルを横軸で見る部門がある、っていう。 |
| 千葉氏 | そうですね。そうしないと、例えば自分がWeb講演会の担当だとして、「Web講演会では安全性情報を得たい先生が多いのか。じゃあそれをメインで講演内容を検討しよう」、で終わってしまう。オムニチャネルでしっかり情報を届けようということなら、チャネル全体、届けるべき情報全体で横断的に考える必要がありますよね。 |
| アリキキ氏 | そのためには、各チャネルでできることをきちんと整理して、上層部の理解を得ることが必要なんです。そのために、担当者は戦わないとダメだって思ってます。実際、私が会社と一番戦ってきた部分はここだったりします(笑) |
(次回に続きます)
「ラボの休憩室」は、DM白書ラボの「エビデンスに基づいた情報提供」とは異なるお試し企画です。
本コーナーの今後の継続は会員のみなさまのご意見で判断したいと思っています。ぜひ下記アンケートにご協力ください。
次回は、ラボの休憩室Vol.2 NO.1ならいいんですか?データの表と裏を見る をお話しします。
(文:松原)