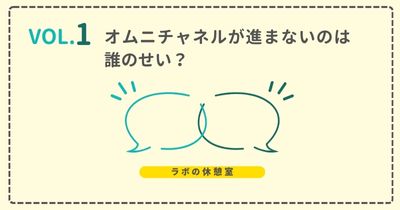ラボの休憩室 Vol.2 NO.1ならいいんですか?データの表と裏を見る
取材年月:2025年4月
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
某製薬企業のDx推進担当。20年以上にわたり、ヘルスケア業界で営業、マーケティング、IT、Dxの多分野に従事。これまでの経験を通じて、普段感じていることを飾らずにお話いただきます。 ■千葉 理洋(仮)
DM白書ラボ フェロー。
PVがこんなにあるので大成功!?ほんとにそうですか?
| 千葉氏 | アリキキさん、引き続きよろしくお願いします。前回のお話※1では、成果指標として数値を追うという話がありました。今回はデータの分析や活用についてお話できればと思います。 |
|---|---|
| アリキキ氏 | そうですね。薬剤のプロモーションって、どういうコンテンツが刺さるかとか、どういう先生方の傾向が多いんだなとか、ポジショニングとか、上市前にさんざんマーケティング部門でリサーチしているわけじゃないですか。そこでメッセージを作って、こういうアプローチしようって、マーケだけでなくメディカルの方々も一緒にコンテンツを作りますよね。こういうコンテンツを作らないと響かない、とか、最初にこういうふうにしていかないといけないって。 |
| 千葉氏 | そうですね、かなり綿密にやられている印象です。 |
| アリキキ氏 |
ただ、その設計をしたあとに、その結果から得られたデータを分析して活用するってところが甘いって僕は思っています。あと、間違った数字っていうか支持証拠の選択的収集※2をしてませんか?って。 「コンテンツ作りました。そのコンテンツのページのPVがこんなにあるので大成功!」ってほんとにそうですか?そのデータは顧客マスターと紐付いていて、CRMを使っていつ誰が見たかまで見れますよね?BIツールが使える環境もありますよね?でも、そこまでしっかり見ていない。 |
- ※1 ラボの休憩室 Vol.1オムニチャネルが進まないのは誰のせい?
- ※2 自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するため、自分にとって都合のよい情報ばかりを集め、都合の悪い情報を無視したり最小限に抑えたりする傾向の認知バイアス
どういうデータで評価するのか
| 千葉氏 |
言われてみると、そういうケースが多い気がします。あと、わたしはデータだけでは顧客の温度感が掴みきれないと思っています。 デジタルデータって扱いやすい反面、真剣に見た1PVなのか、メールが来たからなんとなくクリックした1PVなのか、その温度差はつけづらいですよね。MRさんなら、手ごたえがあった面談とコール的な面談の違いって自分で分かるじゃないですか。受け手の温度差はデジタルだとなかなかつかみきれない。 |
|---|---|
| アリキキ氏 |
そうなんですよ。結局どういうデータで評価するのかというのはすごい悩みどころです。データをそのまま評価してしまうとミスリードにつながってしまう。ノイズを取り除かないといけない。例えばMRさんだと、日報の記載情報も評価の一部になっている場合、「〇〇に関して医師の感触は悪くなかった」とか書いてあると、良いとも限らないじゃないですか? Webサイトだと3rdPartyの「ポイント」の話は必ず出ますし……。 データとして活用する際に不確定要素が多かったり、曖昧なデータを食わせてしまうとアウトプットにずれが生じていくので、それはノイズとして扱う必要がありますよね。 そして、こういったノイズを取り除くデータクレンジング対応者への社内評価が意外と低かったりすることもあり、悩ましいところです。 |
| 千葉氏 | 確かに、私も似たような経験があります。以前、非常に優秀なデータサイエンティストと、利用チャネルとチャネルシークエンスを変更すると、売上がどう変動するかを予測するシミュレーターを作ったときの話なのですが、そのデータサイエンティストが提示してきたデータクレンジングの期間が、こちらが考えていたよりもずっと長かったんですよね。それで「クレンジングにこんなに期間がかかるのですか?」と聞いたら「データ分析においては、ここが一番重要なんですよ!」と真剣に怒られちゃいました。 |
| アリキキ氏 | そうでしょう、そうでしょう。 |
| 千葉氏 | データ分析をしている人からしたら、“いかに分析に値するデータを作るか”が肝なんですよね。 |
| アリキキ氏 | データクレンジングってすごく大切で、ノイズが入り始めちゃうとアウトプットがめちゃくちゃになっちゃって分析に値しないデータになっちゃう。社内のチャネルからの情報を正しく取ってノイズを省いていれば、分析に値するアウトプットが出せるはずなんですよ。でも実際はできてない。 |
| 千葉氏 | そこは担当者のジレンマもある気がします。前回の話※1にあったように「1番目指せ」って数を問われている中で、ノイズを取り除いたら数が1/10になってしまうなら、そのままの数値を評価したい、ということは当然起き得るかなと思いますし。 |
| アリキキ氏 | 数にこだわるとどうしてもメールをバンバン打ったりということをやりがちだけど、受け手からすると既知の情報を一方的に与えられ続けるのってすごくストレスですよね。メールからもMRからもWeb講演会からも、A先生に対して作用機序!作用機序!作用機序!と3連発で送って、そのせいで「もういいよ」ってなってしまうこともある。 |
| 千葉氏 | 確かにそれは嫌ですね。 |
| アリキキ氏 | そこのコントロールでちゃんとできてますか?ってのもあるし。 |
定量データ、定性調査どちらも重要
| アリキキ氏 |
コマーシャルとメディカルは情報を切り分けるべきだ、が行き過ぎた結果、MRの面談記録とMSLの面談記録が完全に別管理になって、同じ医師に同じような情報を提供したり、同じような感じでマーケからも同じような内容のWeb講演会を案内して医師から「またか」と思われている、みたいな。 必要とするところに必要としているものっていうのを届けていくには、それぞれのチャネルのログを正しく入手して、そこに対して無駄打ちをしすぎないことが各チャネルを効果的に機能させるためには必要だと思います。 |
|---|---|
| 千葉氏 |
データの背景とか裏側をしっかり把握できると、データの捉え方も変わってくると思うんです。 前回のオムニチャネルの話じゃないけど、データへの期待値が高すぎるとデータのみで意思決定をしてしまうリスクがありますよね。 |
| アリキキ氏 | そうそう、データに振り回されることもありますね。 |
| 千葉氏 |
定量データの背景や裏側を読み解くためには、定性調査も重要だと思います。定性調査は一部の医師の声でしかないと思う方もいらっしゃいますが、定量データだけで背景や裏側を読み解くのはなかなかに難しい。ですので、アンケートデータ、行動データ、定性調査を組み合わせながら、データの背景や裏側を読み解くのが良いと思うんです。 ここを見誤ると、マクドナルドのサラダマックの失敗※3みたいな話にもなりますしね。 |
| アリキキ氏 | たしかに(笑)。結局、本当の意味でデータを「読み解く」ってことなんじゃないかな。 |
- ※3 マクドナルドが消費者に対してアンケートやインタビューを行った結果、「もっとヘルシーなものを食べたい」と言う声が圧倒的に多く、2006年に「サラダマック」を発売したが大失敗に終わった。アンケートやインタビューの回答と実際の行動にはギャップがあるという分かりやすい事例としてよく用いられる。
(次回に続きます)
「ラボの休憩室」は、DM白書ラボの「エビデンスに基づいた情報提供」とは異なるお試し企画です。
本コーナーの今後の継続は会員のみなさまのご意見で判断したいと思っています。ぜひ下記アンケートにご協力ください。
次回は、ラボの休憩室Vol.3 MR不要論を考える をお話しします。
(文:松原)