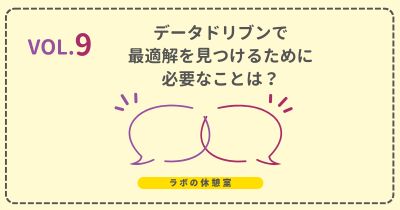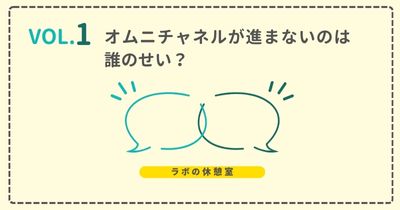ラボの休憩室 Vol.10 データ活用に向けたマインドチェンジの進め方
このコーナーでは、製薬業界のデジタルマーケティングに長年関わってきた方に登場いただき、ざっくばらんにお話していただきます。
なお、本記事に掲載されている意見は、参加者の個人的な見解に基づくものであり、参加者の所属団体や他の関係者の意見を反映するものではありません。読者の皆様は、内容をご自身の判断でご利用いただきますようお願い申し上げます。
取材年月 2025年9月
大手製薬企業、外資系製薬企業にてMRを10年以上経験後、営業部門(MR、マネージャー)の人材育成の担当者としてソフトスキル・オムニチャネルトレーニング、ローンチ時の研修に5年間従事、その後、DX推進者として、本社間、本社-MR間のコミュニケーションのハブとなってプロジェクトマネジメント、チェンジマネジメントを担当。 ■千葉 理洋(仮名)
DM白書ラボ フェロー
学んだことを身に付けるためには?
| 千葉氏 |
前回、データ活用においては、データとKKD※1の両方を受け入れて、目的に対しての最適解を探していくマインドセットが重要だというお話がありました。わたしは、データ分析に限らず、このマインドセットってすごく重要だと思っています。 例えば研修でハードスキルやソフトスキルを学んだとしても、それを実践したり、実践しながら振り返ったりすることはなかなかできないと思うんです。今日はこの「マインドセット」について、人材開発のご経験が豊富なセーダスさんにお話を伺いたいです。 こういったマインドセットってどうやったら身に付くんでしょうか?研修で身に付くものなのでしょうか? |
|---|
- ※1 経験(Keiken)、勘(Kan)、度胸(Dokyo)
| セーダス氏 |
身に付くといいたい(笑) やっぱり、座学とかで学んだことを実践したり行動すること以外の正解はないと思うんです。それができるようになるためには、組織全体として、学んで行動してっていうサイクルを回すことについて合意形成できていることが重要だと思います。それができている上で、トレーナー自らが実践していくことが大切です。トレーナー自身が実践できていないと、例えばロジカルシンキングの研修で、「あいつ全然ロジカルちゃうやん」みたいに思われてしまう(笑) |
|---|---|
| 千葉氏 | 確かに(笑) |
| セーダス氏 |
データ活用のトレーナーは、データサイエンティスト側と現場側どちらも理解し、実践し、行動で見せることで、その世界線を実感してもらうことが必要だと思います。 ただ、現実問題として、データサイエンティストが現場を理解したり、現場の人間がデータサイエンティストになったりするのはハードルが高いですよね。そうなると、わたしのようにデータ活用にビジネスアーキテクト※2として携わった人間がその立場を担うことが必要だと思いますし、そういった人間がもっと増えていくと良いと思います。 |
- ※2 ビジネスアーキテクトとは、デジタル変革(DX)の推進において、目的設定から導入、効果検証までを関係者を調整しながら一貫して推進し、企業全体の戦略実現をリードする人材
「やる気スイッチ」は科学の力で押せる
| 千葉氏 | マインドを変えるには、まずは実践ということですね。わたしも「意識を変えるのが先か、行動を変えるのが先か」という話では、行動が先だと思っていて、意識から変えていくのって相当難しいと思っています。行動があって、そこから意識が変わる。より細かく言うと、行動したあとの振り返りの中で意識が変わっていく。 |
|---|---|
| セーダス氏 | そうそう。 |
| 千葉氏 | ただ、こういう部分って社会人になるまでの経験が大事ではないかとも思っています。社会人になってから身に付けるにはどうしたらいいんでしょうか。 |
| セーダス氏 |
なかなか難しいところですが、やっぱり行動なんだと思います。 「やる気スイッチ」ってありますよね。 あれは脳の淡蒼球という部分が司っていて、「行動」と「報酬」の2つで押されるということが分かっています。思考ではないんですね。 つまり、脳の仕組み上は、「どうやって行動すれば良いか分からない」、「なかなか行動が起きない」といった思考の問題で行動できない、といったことは起きないんです。脳の仕組みを知っていれば、やる気を起こすように脳に働きかけることができますし、思考や性格の問題ではないことも認識できます。科学ってすばらしい(笑) |
| 千葉氏 | やる気がなくても、とりあえず行動するとどうにかなることはありますよね。すごく面倒なことも、着手してしまえばできてしまうというか。とりあえずやればどうにかなるって動き方は大事ですね。 |
| セーダス氏 | そういう意味では、かつてのMRさんが「とりあえず先生のところへ行ってこい!」と言われていたのは理にかなっていたりするんです。半ば強制的に行動し、その後で上司との1on1や日報の中で振り返るという。 |
| 千葉氏 | 実に理にかなっていますね(笑) |
| セーダス氏 |
でも今はそういう時代ではなくなっている。特に若い人に対しては、「なんでやらないといけないの?どんないいことがあるの?」という疑問に答えて報酬を与えるというプロセスが大事です。動機を与えて行動を促し、行動したら考える、それによってマインドセットを身に付けていくんですね。 トレーニングで取り入れるときには、科学で実証されていることを伝えて、マインドセットのきっかけとして使っています。経験論ではなく、サイエンスで人を動かして変えていくことができるんじゃないかなと思っています。 |
金銭的報酬がないと仕事をしないのか?
| 千葉氏 |
「報酬」の話がでましたが、金銭的報酬、社会的報酬※3のどちらがいいのかという議論もあります。 わたしは金銭的な報酬はうまくいかないのではと思っていて、それは、一度金銭的な報酬をつけてしまうと、つかなかったときには効果がないから。m3のポイントと一緒で、つかないときに反動がきてしまう。報酬って難しいと思うのですが、いかがでしょうか。 |
|---|
- ※3 社会的報酬(Social Reward)とは、金銭的なインセンティブとは異なり、他者からの承認や感謝、尊敬といった社会的な評価を通じて得られる報酬のことを指す。これは人間の基本的な欲求の一つであり、職場においてもモチベーションの重要な要因となると考えられている。社会的報酬には、承認(Recognition):上司や同僚からの感謝や評価、尊敬(Respect):組織内での信頼や影響力の向上、所属感(Belonging):チームの一員として認められること、社会的比較(Social Comparison):他者と比較して優れた成果を出したときの満足感がある。
| セーダス氏 | わたしはもともとリーダーシップ開発をしていたのですが、そのときは、金銭的報酬でもいいと感じていました。 |
|---|---|
| 千葉氏 | そうなんですね。それはなぜでしょうか。 |
| セーダス氏 |
リーダーシップ開発では「あなたはなんで仕事をしているの?」と投げかけるのですが、6~7割は「お金のため」という答えが返ってきます。ですが、「なぜお金がほしいのか」を本人が理解していると、金銭的報酬が無くなっても本質が理解されているから大丈夫なんです。 お金が欲しい、なぜなら旅行したいから、旅行することで、その場所で得られる経験をしたいから……、というように、金銭を通じてどんな自己実現をしたいのか、を明らかにしていくのがリーダーシップ開発です。 金銭はきっかけ、手段でしかなくて、「その手段を通じて自分はどんな自己実現をしたいのか?」が大事です。それが見えていれば、たとえお金が無かったとしても違う手段を自分で見つけられます。 |
| 千葉氏 | 「お金がすべて」ではなく、お金を通じて自分が何を実現したいのかを理解できていれば、金銭的報酬でも良いということですね。 |
| セーダス氏 | 「お金が欲しい、お金が無くなった、やりません」ではダメ。そういう意味では、自己理解※4というのは目には見えませんが、すごく大切だと思っています。 |
- ※4 さまざまな手段を用いて自分自身の性格や気質、タイプや考え方、価値観などを深く知り、それを自分自身の特性として受け止めること。自己理解を深めれば、自己の変化のきっかけをつかめたり、他者へ意識が向けられるようになったりする。
「7割でGO」ができない、製薬企業のDX推進の壁
| 千葉氏 | データ利活用のためのマインドセットについて伺ってきましたが、データ利活用を推進していく上での理想と現実のギャップについて教えてください。 |
|---|---|
| セーダス氏 | 理想的な姿は、いろんなファンクションが役割分担しながら、戦略のKPI、KGIを検証し、結果・状況に応じてデータドリブンで意思決定、改善されるサイクルを回していけることだと思います。 |
| 千葉氏 | そういったやり方は、年間単位の大きな戦略では良いと思うのですが、PoC※5ではスピード感がでないこともあるのではないでしょうか。 |
- ※5 Proof of Concept:概念実証。新しいアイデアや技術の実現可能性や効果を検証するためのプロセス。
| セーダス氏 | そうなんです。そこが製薬企業のDXが進んでいない最大の要因だと思います。 |
|---|---|
| 千葉氏 | なるほど。「ちょっとやってみよう」は難しい? |
| セーダス氏 |
7割でGOすることができない、検証に時間をかけすぎている。期間の問題もありますが、領域・製品によってデータサンプルが集まらなくて分析できないというのもあります。そこが悩ましいし、一番悩んでいます。 “2~3か月やりたいことのPoC を半年かけてやるんですか?”という話で、では実際どうしたらいいのかがわからない所です。 結局は経営側が何をしたいのかという意志が大事で、「7割でだいたいいいじゃん。やろう。」という強い意志がないと難しいと思っています。 「患者さんに薬を届けるのに有効」ってみんなが思えるビジョンが見えていたらいい、とわたし自身は思いますけど、簡単ではないし正解がないんです。 |
| 千葉氏 | 社内外どちらも同じような形ですか? |
| セーダス氏 | DXは社内でも社外でもスタンスが同じなんですが、社外の案件でやるのはリスクがあるので、社内の部分では「7割でやっていこう。徐々にPoC を回していこうよ」という風土を作っていって、徐々に風潮を変えていくことが大事だと思っています。 |
| 千葉氏 | デジタルのような、業界として今までなじみの薄かったものに対して決断しづらいという風潮はあるのではないでしょうか。製薬業界には、トップマネジメントと同列で話せるデータやデジタルのスペシャリストが必要ではないでしょうか。 |
| セーダス氏 |
幸い、弊社にはそういったスペシャリストがいるのですが、そこは大事だと思っています。「7割でやっていこう。」ということについても、どの事業部も拒否するわけではないので、まずは受け入れられる事業部でやる、そしてエビデンスを出す、ということが大事だと思っています。 ブレーキをかける要因には、何か不都合が起こった時の責任の重さもあります。最終的に患者さんに影響してしまうことは絶対に避けなければいけませんから。ただ、責任を負いたくないというところから、役割を細分化して、責任の所在を不明瞭にしている……という別の問題もあったりして、なかなか難しいなと思います。 |
ドクターを神格化しすぎている?
| 千葉氏 | 顧客である医師にどう受け取られるかという部分も、慎重さに繋がっていると思うのですが、製薬企業の方は医師を神格化しすぎているんじゃないかって思うんですよね。 |
|---|---|
| セーダス氏 | それはどういう……? |
| 千葉氏 | 先生に、「薬剤の処方の検討度合い」を5段階で聞く定量調査※6として、最も上が「不動産」、次に「高級車」「海外旅行」「高級レストラン」「家族へのプレゼント」という選択肢を用意したところ、最も多かったのは「海外旅行」で3割、次点が「家族へのプレゼント」3割でした。ラボチームでは「高級車」か「不動産」が最多ではと予想していたのですが……。 |
- ※6 「処方における検討レベル(仮)」2025年12月DM白書ラボ公開予定
| セーダス氏 | 特定の診療科の先生に聞いたんですか? |
|---|---|
| 千葉氏 | いえ、医師5,000人の大規模調査です。診療科別や施設形態別などでセグメントを切ってみたのですが、比率はそんなに変わりませんでした。 |
| セーダス氏 | 「海外旅行」……。まぁ先生にとっては毎日数多く行っている判断のうちの1つですもんね……そうかぁ(笑) |
| 千葉氏 | 先生はこちらが思うよりも気軽に薬剤を決めているのだとすると、コミュニケーション手法やその内容も変わってくるし、もっといろんなことができるんじゃないかって思うんです。今の上層部の方々が医師とやりとりしていたころとは、医師と製薬企業の力関係も変わってきているのかなと思います。 |
| セーダス氏 |
たしかにそうかもしれません。製薬企業のコアバリューとして医師にとって重要な存在でありたい、その自負を持つべき、という企業姿勢も大きいんじゃないかなぁ。 そうかぁ。たしかに、毎日高級車を買うような決断をしていたらしんどいですもんね(笑) |
次回は、ラボの休憩室 Vol.11 オムニチャネル時代のMRに必要なマインドセットって? をお話しします。
(文:松原)