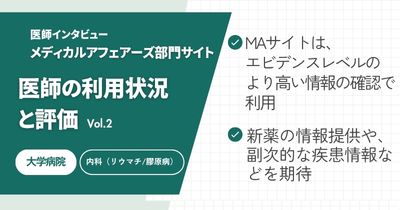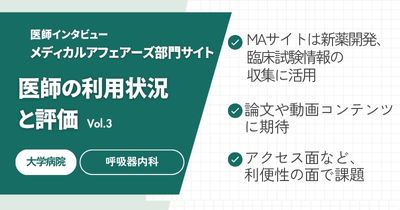メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.1 国公立病院 勤務医編
取材年月:2025年4月
メディカルアフェアーズ(以下MA)部門からのデジタルを介した情報提供は、医師にどのように利用されているのでしょうか。本記事では実際にMA部門のサイトを利用している医師に、MAサイトで得ている情報、閲覧している製薬企業のMAサイトごとの評価と要望および、MSLとの面談状況についてお話を伺い、MA部門における医師ニーズに沿ったデジタル活用の方向性について考察していきます。
今回は、国公立病院消化器内科・腫瘍内科に勤務されるS先生のインタビュー内容をご紹介します。
現在、製薬企業MA部門のサイトは掲載内容、サイト構造ともにさまざまです。本インタビューでは、MA部門のサイトを利用している医師を対象に、サイトの利用状況および評価を具体的に伺い、MA部門サイトの在り方を探ります。
目次
- ● MAサイトの主な利用目的は安全性情報の取得。また、薬剤の有効性や、FDAで承認された薬剤情報、研究に関する情報も確認している。
- ● MSLからは、臨床研究に関する情報提供を受けているが、MSLとMAサイトの連動の必要性は感じていない。
- ● MAサイトに今後望むことは、治療全体に関わる幅広い情報の掲載。テキストより動画コンテンツを充実させてほしい。
メディカルアフェアーズ部門のサイトと製薬企業サイト(プロモーションサイト)は、意識して使い分けていない
よくご覧になるメディカルアフェアーズ部門のサイトについて教えてください
製薬企業A社と製薬企業B社のサイトです。どちらも月に1回以上閲覧しています。
製薬企業A社のサイトは、専門領域の治療薬で適用拡大があったのが5年以上前かと思いますので、その頃から見ています。
メディカルアフェアーズ部門のサイトを利用する目的はどのようなものですか。
主に安全性情報を取得したくてチェックしています。わたしの専門は胃がんなので、がん免疫治療薬の安全性情報を見ることが多いですね。薬剤の有効性や、FDAで承認された薬剤情報、研究に関する情報も確認しています。
メディカルアフェアーズ部門のサイトへはどのようにしてアクセスしますか?
検索経由でアクセスします。「製薬企業名」「薬剤名」「サイト名称の一部」などをキーワードとして入力しています。お気に入りには登録していません。
メディカルアフェアーズ部門のサイトを知ったきっかけを教えてください。MRやMSLから案内があったのでしょうか?
いいえ。MRやMSLから案内があったわけではなく、医療従事者向けサイトを見ていたときに自分で発見しました。
医療従事者向けサイトも見ていらっしゃるということですが、医療従事者向けサイトとメディカルアフェアーズ部門のサイトは意識して使い分けていますか?
特に意識していません。安全性情報を調べる場合、関連するキーワードで検索する、検索で表示された製薬企業のサイトを見る、という流れです。アクセスしたサイトが「医療従事者向けサイト」なのか「メディカルアフェアーズ部門のサイト」なのかは、特に気にしていません。改めて見ると、メディカルアフェアーズ部門の情報だと思っていたものが医療従事者向けサイトに載っていたりしていますね。企業サイトや薬剤専用のサイトもあるんですね。特に意識して使い分けているわけではありませんでした。
特定の情報を知るために、あえてメディカルアフェアーズ部門のサイトへアクセスすることはないということでしょうか。
はい。「どの部門が提供しているサイトか?」は特に意識していませんでした。
メディカルアフェアーズ部門のサイトでは論文情報を掲載しているケースもあります。論文を確認する場合にメディカルアフェアーズ部門のサイトをチェックすることはありますか?
いいえ。論文はPubMedなどのほかのサイトで閲覧しているので、わざわざ製薬企業のサイトで調べません。
MSLとメディカルアフェアーズ部門のサイトを連携した情報収集は行っていない
MSLとは面談していますか?
はい。MSLからは、臨床研究に関する情報提供を受けています。現在使用している薬剤の基礎実験や新しい論文情報などが主な面談内容です。製薬企業B社のMSLとは2ヵ月に1回程度、製薬企業C社のMSLとは3ヵ月に1回程度リアルで面談しています。
サイトをよく見ている製薬企業AのMSLとは面談されていないのでしょうか。
そういえば製薬企業A社のMSLとは面談していないですね。コ・プロモーション先の製薬企業のMSLが訪問してくれています。
MSLからメディカルアフェアーズ部門のサイトの案内はありますか?
MSLからサイトを案内されたことはありません。面談後、メールで面談内容に関する論文のURLを送付してもらうことはあります。
複数の製薬企業のMSLと面談されていますが、例えば1回の面談で複数社のMSLと一緒にディスカッションしたい、というような要望はありますか?
いいえ、製薬企業ごとに面談したほうがよいです。複数社のMSLと一緒に話したいという希望は特にありません。
先生はMSLとの面談も定期的に実施されていますが、MSLの動きとサイトが連動していると便利だと感じられますか?例えば、メディカルアフェアーズ部門のサイト上でMSLとのやりとりが管理できるという機能があると便利でしょうか?
現在、MSLとはメールでやりとりしていますが特に不便さは感じていません。MSLとのやりとりがサイト上で管理できるといった機能には、今のところ必要性を感じません。
本音を言うと、現在紙でもらっている論文をPDFデータで欲しいですね。権利の問題で難しいと聞いていますが、メールで送ってもらっている論文情報がサイトにあるとよいのにとは思います。
メディカルアフェアーズ部門のサイトは、情報の幅が広く内容が充実していると高評価
ここからは、普段S先生がご覧になっているメディカルアフェアーズ部門のサイトを10点満点で評価していただきたいと思います。まず製薬企業A社のサイトはいかがでしょうか。
評価ですか。製薬企業のサイトはどれもよくできていると思いますので点を付けるのは難しいですねぇ。「メディカルアフェアーズ部門のサイト」としてじっくり見たことがなかったので、改めてサイトをよく見てみますね。
評価は9点です。
理由を教えてください。
製薬企業A社のサイトは、領域別に大きく分類されていて情報が探しやすい点、また、薬剤のことだけでなく、「診療のコツ」といった治療全体に関わる情報もあり、幅広く充実しているコンテンツ内容である点、それらが動画で掲載されている点が評価ポイントです。サイトの見た目にカラフルな写真(サムネイル)が使われている点も好印象です。カラフルなほうが「見てみようかな」という気持ちになります。好みの問題ですが。
続いて、製薬企業B社のサイトを10点満点で評価してください。
こちらもじっくり見てみます。
評価は6点です。
わたしの専門である胃がんの情報が少ない点が製薬企業Aと差が出た理由です。また、製薬企業Bのサイトの色は同じ色で統一されているのですが、カラフルなほうがいいなと思います。
メディカルアフェアーズ部門サイト採点結果
| 製薬企業A | 製薬企業B | |
|---|---|---|
| 採点 | 9点 | 6点 |
| 評価ポイント コンテンツ |
薬剤のことだけでなく、「診療のコツ」といった治療全体に関わる幅広い情報がある 動画コンテンツで掲載されている |
胃がんの情報が少ない |
| 評価ポイント デザイン |
領域別に大きく分類されていて情報が探しやすい点 サイトの見た目にカラフルな写真(サムネイル)が使われている点 |
単色で統一されている |
市販後臨床研究情報の提供は、「非常に面白い」
では、評価対象にならなかったメディカルアフェアーズ部門サイトのコンテンツについてお話を伺いたいと思います。まず、市販後臨床研究情報としてUMINへのリンクなどを掲載しているケースもあるのですが、どう思われますか?
臨床研究情報をまとめているページがあるんですね。今見ている製薬企業のサイトにあるのに気づいていませんでした。とてもよいですね。このページからUMINのページに行けるんですねぇ。面白いですね。UMINのページは見ますが、製薬企業のサイトからアクセスすることはなかったので、こういった取り組みは面白いと思います。
こういった情報が、現在先生が利用している製薬企業から提供された場合、今後利用されますか?
頻繁ではありませんが、見ることもあると思います。今どのような研究が進行中なのか、製薬企業の臨床研究の状況が一覧で確認することができる点がよいですね。
市販後臨床研究情報の提供が、処方にポジティブに働くことはありますか?
そこまではないです。一覧を見て「へえ、なるほど」と思うくらいですね。
学会ランチョンセミナーの配信は「ぜひやってほしい」
メディカルアフェアーズ部門のサイトで、学会のランチョンセミナー動画を掲載しているケースもあるのですが、どう思われますか?
学会のランチョンセミナーは、興味のある内容でも時間帯が被っていて参加できないことも多くて残念に思っていたので、ランチョンセミナーの配信はよいですね。結構勉強になる内容が多いので配信してもらえるととても嬉しいです。
動画以外に、記録集など静的コンテンツは必要でしょうか?
学会の記録集も結構役に立ちます。海外学会の日本語でのまとめやFigureを載せてくれると、あとから見返すときに助かります。
メディカルアフェアーズ部門からは、幅広く、わかりやすい情報提供を希望
では、最後にメディカルアフェアーズ部門のサイトから情報提供について要望があればお伺いしたいです
治療全体に関わる幅広い情報があるとよいと思います。テキストより動画コンテンツが充実している方がわかりやすくて好みです。メディカルアフェアーズ部門主催のWeb講演会のアーカイブや、先ほど話題に上がった学会ランチョンセミナーの配信も実施してほしいです。
医師だけではなく、オンコロジー領域の薬剤師など、医師以外の医療スタッフに向けたコンテンツがあってもいいのではないでしょうか。
ラボ編集部より
薬剤情報の主な収集チャネルはインターネット経由、MSLとの定期的な面談でメディカルアフェアーズ部門と接点のある医師であっても、「メディカルアフェアーズ部門のサイトからの情報」を明確に意識して利用しているわけではないことが明らかになりました。
メディカルアフェアーズ部門のサイトからの情報提供内容について、S先生の評価が高かったのは以下です。
- ● 治療全体に関わる幅広い情報
- ● 動画中心のコンテンツ
- ● 領域別など情報が探しやすいこと
- ● 学会ランチョンセミナーの配信
メディカルアフェアーズ部門サイトで提供すべき内容や手法については、医師の利用実態やニーズを把握する必要があります。
今後解決すべきことは?
次回は、メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.2 大学病院 勤務医編 をご紹介します。
(文:松原)