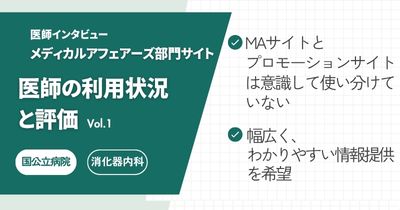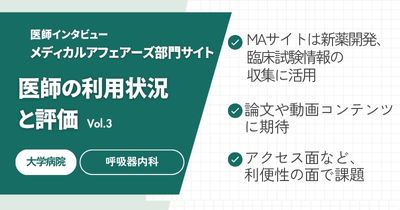メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価 Vol.2 大学病院 勤務医編
取材年月:2025年5月
メディカルアフェアーズ部門(以下MA)からのデジタルを介した情報提供は、医師にどのように利用されているのでしょうか。本記事では、実際にMA部門のサイトを利用している医師に対して、MAサイトで得ている情報、閲覧している製薬企業のMAサイトごとの評価と要望、さらにMSLとの面談状況についてお話を伺い、MA部門における医師ニーズに沿ったデジタル活用の方向性を考察します。
今回は、大学病院内科(リウマチ、膠原病)に勤務されるK先生のインタビュー内容をご紹介します。
現在、製薬企業MA部門のサイトは掲載内容やサイト構造が多岐にわたります。本インタビューでは、メディカルアフェアーズ部門のサイトを利用している医師を対象に、サイトの利用状況と評価を具体的に伺い、メディカルアフェアーズ部門サイトの在り方を探ります。
目次
- ● メディカルアフェアーズ部門のサイトの利用目的は、エビデンスレベルのより高い情報の確認。利用タイミングは新薬発売、適用拡大、長期処方制限解除のタイミング。
- ● メディカルアフェアーズ部門のサイトに期待するのは、MRだけでは不足する新薬の情報提供や、副次的な疾患情報、専門外の領域における疾患の概念を解説する動画
- ● メディカルアフェアーズ部門のサイトでしっかり情報提供している企業に対してポジティブな印象を持ち、処方意向にも影響を与える
メディカルアフェアーズ部門のサイトではよりエビデンスレベルの高い情報を得たい
先生がよくご覧になるメディカルアフェアーズ部門のサイトについて教えてください。
半年に1回程度、製薬企業A社とB社のサイトを閲覧することがあります。また、製薬企業C社のサイトも時折見ることがあります。
各社のサイトを実際の画面で教えてください。閲覧しているサイトはMAサイトでしょうか?
はい。A社とB社はMAサイトを閲覧しています。ですが、C社はプロモーションサイトの方を見ていました。サイトが分かれているんですね。C社のMAサイトは見たことがありませんでした。
先生の専門領域ですとA社、B社以外にも薬剤を販売している製薬企業がありますが、なぜA社とB社以外のMAサイトを見ていないのでしょうか?
C社とD社の薬剤も使用していますが、それらの企業は MRが来るので、サイトで情報収集しなくても済んでいます。コロナ禍以降、A社とB社はMRと会う機会が減っているため、サイトでの情報収集を行っています。
では、今回はA社とB社についてお話を伺います。2社のMAサイトはいつごろから利用されていますか? また、サイトを知ったきっかけも教えてください。
どちらのサイトも4~5年前のコロナ禍のころから利用しています。A社は分子標的薬の適用拡大がきっかけで、薬剤の用法用量やエビデンスなどを調べている中でMAサイトを見つけました。B社は当時、わたしの専門領域の新薬を開発しており、学術担当者と接点があったんですね。そのときに、担当者から紹介されたデータを自分でも確認したくて探していた時に、サイトを見つけました。
B社もMAサイトはご自身で見つけたのですね。
はい、学術担当から教えてもらったわけではありません。
MAサイトはプロモーションサイトと比べると、少し見づらい点もあるのでは?と思いますが、ご覧になったときの感想を教えてください。
最初の印象は、「見にくい」「アクセスしにくい」「押す場所がたくさんあって、どうやって使っていいのかよくわからない」というものでした。ただ、自分の臨床経験が増えてきて、基礎研究にも関わるようになったため、こういった情報が非常に勉強になると感じています。
MAサイトにはどのようにアクセスしますか?
どちらもブラウザから、「企業名」「薬剤名」などで検索してアクセスします。ブックマークはしていません※1。
- ※1 両サイトともプロモーションサイトのメインナビゲーション上にメディカルアフェアーズ部門のサイトを設置する導線
MAサイトではどのような情報を確認しますか?
どちらも薬剤基本情報やエビデンスを確認したいときにアクセスしますが、A社のサイトでは専門領域の薬剤に関する、エビデンスレベルのより高い情報を確認します。
B社のサイトでは専門外(専門に関連する副次的な領域)というわけではありませんが、例えばわたしの場合は「膠原病専門だが骨粗鬆症を調べる」、といったときに情報を確認します。B社のサイトで確認する情報は、主に病態生理や、既存の薬剤でのアプローチ方法、エビデンスなどです。
MAサイトで情報収集するタイミングを教えてください。
A社は専門領域の新薬発売、または適用拡大のタイミングです。B社は副次的な疾患の薬剤について調べることが多く、頻繁に使用する長期処方制限解除のタイミングに情報収集を行っています。
処方検討段階は、薬剤の比較検討をしている段階、薬剤使用開始前、トライアル処方の段階で情報収集します。使い慣れてくると臨床で困ることはあまりないため、MAサイトは見ません。
2社で取得する情報やタイミングが異なるのはなぜでしょうか?
これは各社の薬剤自体の内容に起因するもので、2社のサイトの構造や情報提供内容の差が原因ではありません。
製薬企業オウンドサイト(プロモーションサイト)とMAサイトは意識して使い分けていますか?
結構難しいですね。MAサイトの情報は、エビデンスを中心とした客観的な指標があると思っていて、製薬企業オウンドサイト(プロモーションサイト)の情報は、MRが提供してくれる内容に近いという認識です。
検索からたどりつくこともありますし、意識的に見に行くこともあります。今は大量の情報の中から信頼性のある情報を取捨選択しなければならないため、製薬企業が発信している情報かどうかは重要視しています。
医療系ポータルサイトとはどのように使い分けていますか?
明確には使い分けてはいません。医療系ポータルサイトは複数の製薬企業の情報が掲載されており、受動的・能動的に情報を得られることもあり、かなり使いやすいと思います。関連する製薬企業とのつながりや、普段あまり関わりのない製薬企業とのつながりも持てます。コロナ禍以降、医療系ポータルサイトでの情報収集は一段落した感がありますが、使いやすいことには変わりないですね。
先生が知りたいエビデンス情報が医療系ポータルサイトに載っていれば便利でしょうか?
はい。医療系ポータルサイトと製薬企業のサイトの情報の質は同等と考えていますので、医療系ポータルサイトにすべての情報が集まっていれば非常に便利だと思います。
MRと異なり、MSLは情報提供までにタイムラグがあるのが難点
MSLから情報を得ることもありますか?
新薬情報などのMRから得られない情報は、MAサイトで確認するか、MSLから情報を得ることになります。MSLと話せればその場で疑問を解決できるので助かりますが、MSLは予約制なので情報を得るまでにタイムラグが生じることが難点だと思います。
情報提供のスピード感について、MSLとMRに差があると感じますか?
はい。MRはメールなどで翌日には情報を届けてくれるので、「待たされる」という感覚を覚えたことはありませんが、MSLは時間がかかりますね。
MAサイトの内容に疑問がある場合はどのようにされていますか?
実は結構困っています。MSLだとタイムラグがでてしまうため検索やAIを使って調べてはみますが、信憑性の点で問題があるなと感じています。頻繁に起こるわけではありませんが。
MSLとはリアルで面談されていますか
面談はリアル・リモート両方とも行うことはありますが、リアルのほうが多いかもしれません。
リアルとリモートではどちらがやりやすいですか?
そうですね。リモートは通信の問題や、モニターや音声環境を準備しないといけない、話が漏れない場所で行わないといけない、といった制約があるので少しやりづらいなと思う点はあります。
MAサイトはコンテンツ内容や見やすさがどちらも評価対象
ここからは、K先生が普段ご覧になっているMAサイトを見ながらお話を聞かせてください。まず、A社のサイトについて10点満点で評価してください。
難しいですね…。じっくり見てみます。
評価は7点です。ほどよく使いやすいのですが、どこに何があるのか見づらい点が気になります。A社のサイトでは以前に臨床研究や基礎研究の情報を閲覧したことがあり、かなり勉強になりました。治験や臨床研究一覧は利用したことはありませんが、今どのような研究が進んでいるのか、世の中の動きを知ることができる点が有用だと思います。
製薬企業B社のサイトはいかがでしょうか?
はい。見てみますね。
こちらも評価は7点です。
A社と異なり、疾患や薬剤ごとに掲載されているため、入り口がわかりやすい点が良いですが、A社とB社のどちらの方が優れているかという認識はありません。
メディカルアフェアーズ部門サイト採点結果
| 製薬企業A | 製薬企業B | |
|---|---|---|
| 採点 | 7点 | 7点 |
| 評価ポイント コンテンツ |
臨床研究、基礎研究の情報が勉強になる 治験や臨床研究一覧は、進行中の研究について知ることができ有用 |
― |
| 評価ポイント デザイン |
どこに何があるのか見づらい | 疾患、薬剤ごとに掲載されているのでわかりやすい |
A社のMAサイトにある市販後臨床研究結果のページは利用したことがありますか?
見たことがあるという程度で、利用したことはありません。このページに遷移したら「あっ!間違えた!」と思って引き返すかもしれません。
先生がご利用されていないMAサイトでは、学会共催セミナーのオンデマンド配信を行っているケースもあります。こういった情報を利用したいと思われますか?
ありがたいと思うし勉強になるとは思います。ただし、当然内容にもよりますが、利用したいか?と聞かれると難しいところです。視聴のための時間を確保できるかなぁと思ってしまいました。自分も経験を重ねてきて、動画の準備や配信に手間とお金がかかっていることがわかってきたので…そこまで重要な情報提供なのかな、と疑問に思う気持ちもあります。学会共催セミナーにはCOIを感じることもありますし。
MAサイトが充実している製薬企業にはポジティブな印象を持ち、処方意向にもつながる
MAサイトへ期待する点はどのようなことでしょうか。
お話ししてきて、MAサイトとプロモーションサイトの境がよくわからないなと感じました。MAサイトが何を目的に作られているのかも分かりづらいです。
MAサイトを見るということがあまり日常的に浸透していないので、疾患情報や学会共催セミナーのアーカイブ動画などは、プロモーションサイトにあってもいいのではないかなと思いました。もちろん、製薬企業のさまざまな制約があるのだろうなということはわかりますが、MAサイトにはアクセスしづらいのでたどりつけていない情報もあり、もったいないなぁと思います。
今のサイトの構造は分かりづらいと感じられますか?
はい。開発中の薬剤がプロモーションサイトに混ざっているのはおかしいですが、発売後の薬剤情報は1カ所にまとめてほしいですし、サイトの入り口自体は1つの方が分かりやすいと思います。
臨床研究や基礎研究の情報が役に立ったとのことですが、情報提供の形態は動画がよいでしょうか?
はい。動画は非常に勉強になります。情報が頭に残りやすいという点がいいですね。
情報提供内容としては他に期待する点はありますか?
MRだけでは不足する新薬の情報提供や、副次的な疾患情報、専門外の領域における疾患の概念を解説する動画があると嬉しいです。論文や臨床試験の羅列は、わたしはあまり必要性を感じません。
今後、適用拡大が見込まれるニッチな自己免疫疾患の分子標的薬に関する情報は、やはり製薬企業サイトから得たいので、情報の充実をお願いしたいです。
先生は、MAサイトでしっかりと情報提供を行っている製薬企業に対してどのような印象を持たれますか?
それはもちろんポジティブな印象を持ちますし、それが処方意向にも影響を与えます。情報提供がしっかりなされている製薬企業には良い印象を受けます。どの会社もサイトでの情報提供は行っていると思いますが。学会で企業ブースが盛況な製薬企業に対して「しっかりされているんだなぁ」と感じるのですが、それと同じ感覚です。わたしは地方に勤務しているため、サイトでより早く正確な情報が得られるようになることを望んでいます。
ラボ編集部より
前回に引き続き、K先生は製薬企業オウンドサイト(プロモーションサイト)と、メディカルアフェアーズサイトの立ち位置の違いを漠然と認識しているものの、明確な使い分けを行っていないことが分かりました。
K先生がメディカルアフェアーズ部門のサイトに期待する点は以下の通りです。
- ● 臨床研究や基礎研究の情報提供
- ● 承認前の薬剤情報
- ● 専門領域のエビデンス情報
- ● 専門領域の副次的な疾患に関する基本的な情報(病態整理、既存のアプローチ方法、薬剤情報、エビデンス)
- ● 動画中心のコンテンツ
- ● 1つの薬剤情報を、1つの場所で取得できるようにしてほしい
生成AIを含めデジタル上の情報が氾濫している現状において、医師たちの間でより精度の高い情報を短時間で得たいというニーズはK先生に限らず存在しています。その中で製薬企業からの情報提供は、医師から強い信頼を得ていることも過去の医師インタビューでも明らかになっています。
MAサイトの役割として、信頼性の高い情報を提供することに加え、情報へのアクセスのしやすさについても再考する必要があると言えます。
今後解決すべきことは?
次回は、メディカルアフェアーズ部門サイトにおける医師の利用状況と評価Vol.3 大学病院 勤務医編 をご紹介します。
(文:松原)